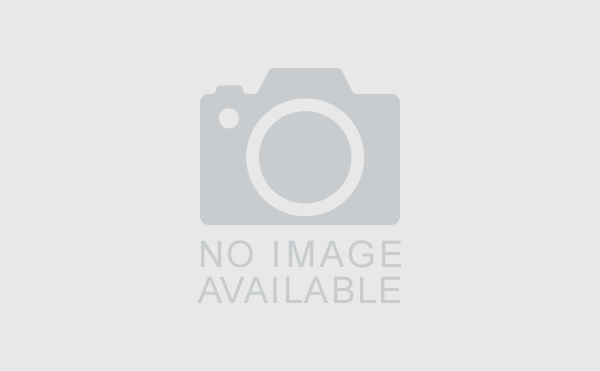「アラマタ図像館②解剖」を読みました。学芸大学の古本屋で荒俣宏の本見つけました。荒俣さんの本は久しぶりです。この本はほぼ解剖図を羅列している本で説明文は十数ページしかありません。図鑑と言えば図鑑という本です。気味の悪い解剖図鑑です。妊娠中の女性の解剖値などでは、子供の内臓なども含まれています。ただ詳細な血管とか皮膚を描写を見ると、これはもう芸術ではないかとも思えます。
日本の解剖図は少ないんですが、西洋とは全く違う考え方で人体内容を表現しています。荒俣さんは日本の解剖図の方が陰陽五行説に影響されていて生活に密着した生き方に関わる解剖図になっていると評価しています。漫画に近い表現です。ヨーロッパのものでは、アルミヌスの「人体筋骨構造」が優れていると感じました。骸骨のバックにインドサイ使われています。これはもう芸術に近いと思いました。
あくなき人体に対する興味が16世紀のレオナルドダヴィンチの描写以来、たくさんの芸術家、科学者が人体解剖図に取り組んでていたことを知り大変驚きました。杉田玄白の解体新書これに影響されて書かれたことは有名な事実です。備忘します。
「君の作品はもう古いや」この一言でモダンなアーティストは即死してしまうことなのです。しかし、新しいことのどこにそんな価値があるのでしょうか?…すなわち古い定型を破るという破壊の論理にのっているのです。裏を返せば、古いものは陳腐化して悪くなるから、新しいものを良いという理屈にもなります。この見解の正しさは近代の人間観によって実証されました。老人は、若者に比べて役立たずなのです。特に高度産業社会となった現在では、老人は労働力になり得ないので、無意味どころか有害とまでみなされるようになりました。アートの世界でも、そうした近代産業社会の都合が優先されたわけです。けれども、少なくとも18世紀まで世界の文学や美術、そして音楽や芸能などを貫いていたルールは、「形に従う」、型をなぞらえる」、「型を守る」ことでした。文学には定型詩がありました。美の基準を作る原理がありました。美をイメージさせる修飾の方法まで、きっちりと決まっていました。ページ17
さて、レオナルドダヴィンチは以来の西洋解剖図が、もっぱら、医学者と美術界用の資料として制作されたのに対し、江戸の人体地図ともいえるこれらの解剖図は、明らかに一般市民用に作られており、何よりも見世物となっている点が驚異である。もちろん、すでに記したように、実は西洋でも、解剖は教育的な見せ物として人気があり、学生の解剖実習が終了すると、入場料をとって死体や臓腑を見せたが、残念なことに西洋には、中国の五行システムに匹敵する万能の「連鎖的知識体系」が存在しなかった。だから解剖死体は、「生命の儚さ」「死の恐ろしさ」といった哲学を教授する教材として、市民に対し活用されたに過ぎない。その点、五行システムを介して、内蔵一つ一つが病気、季節、方位、食べ物、宇宙といったあらゆる現象と関連付けられる日本人は、誠に幸福だった。ページ226