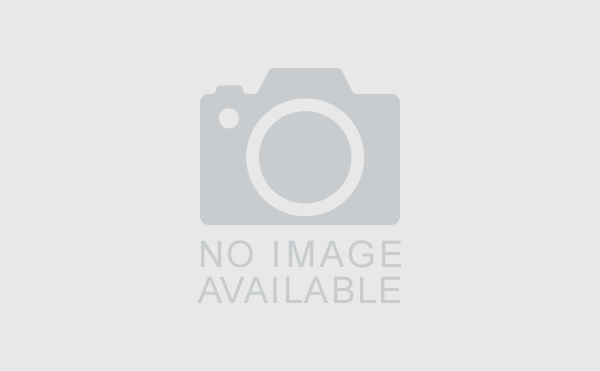「フィットネス・マインドセット」を読みました。副題に「健康と幸せのための考え方」とあるように、著者の谷内直人さんが書かれたこの本は、まさに現代の「養生訓」心得版といえます。谷内さんは私の畏友であり、彼の能力や胆力、人柄に申し分がありません。長年のお付き合いですが、今回の著作も彼の人柄がよく表れており、その点で非常に感銘を受けました。
この本のメインテーマは「頑張らない」という点にあります。人間の意思薄弱さを前提に、無理せず継続できるアプローチが提唱されています。「運動する」よりも「体を動かす」といった表現が、実際に行動を続けるためにはより適していると述べています。また、継続のためには心をセットし直す必要があるとも強調されています。
また、このように一見淡々と書かれていますが、本を執筆すること自体が大変な作業であることを感じます。
巻末の「おわりに」では、谷内さんの若かりし頃の奮闘が描かれており、私にとっても新しい発見がありました。学生時代の興味や大学入学の経緯、スケートや音楽への関心、そして前職について、恨み言ひとつなく、前向きな姿勢が溢れており、彼の魅力をさらに感じることができました。
これから谷内さんが歳を重ねるにつれて、「あきらめ」(加齢)というテーマにどう向き合うのかも楽しみです。備忘します。
「タレントの高田純次氏の言葉にこのようなものがあったとおぼろげながら記憶しています。「年取ったらしちゃいけないものは、説教、昔話、自慢話」…まさに筆者自身もあまり遭遇したくないことであるが故に、大変感心したのを記憶しています。前書き
…本書を通して申し上げたいのは、しつこいようですが、自分で試行錯誤して考えてくださいということです。考えたり試行錯誤するのが面倒だから、手っ取り早く具体的な方法を教えてほしいというのが人情でしょうが、自分に合っていなければ続きません。継続は力なりと言いますが健康づくりもこれは当てはまる、大きな要素の1つです。前書き
…フィットネスってどういう意味でしょうか。いろいろな解釈があるでしょうが、一言で言うと「体力」と表現できます。…「体力」は大きく「行動体力」と「防衛体力」に分けられます。「行動体力」は筋力や持久力、瞬発力など日本人なら身に覚えがあるであろう、義務教育時代の体力テストで測定する項目の力を指す、と思えばわかりやすいでしょう。…防衛体力は体温や食欲の維持、風邪を直そうとするなど、恒常性を保つための力を差します。…フィットネスが良い状態、フィットしている状態は、この2つの体力要素がともに良い状態であると考えましょう。ページ18
それぞれが良いコンディションになっていることを「ウェルビーイング」とも表現します。良い状態にあるという解釈がシンプルでわかりやすいです。…「健康とは身体的、精神的、社会的に完全に健康な状態であり、単に病気や虚弱がないことではない」と記されていますが、この完全に健康な状態を原文ではウェルビーイングとしています。ページ19
フィットネスクラブは、元気な人がより元気になるために、また元気を維持するために通うのだと感じます。筆者が本当に通って欲しいのは、運動が続かない人、最初から運動取り入れないと決めている人なのですが、門戸は開いているものの、クラブは取り込めていないのが現状です。若年層はファッション感覚で、かつ行動体力が高まる楽しさを感じ、中高年齢層は防衛体力を高め、健康維持増進を目的とする大きな流れがあります。なかなか参加率が増えないのは、人々の健康を維持増進し、よりフィットしてウェルビーイングな状態になってもらいたいという理想がありつつも、サービス業、エンターテイメント業から広がりきれないなのだと思います。ページ24
ビジネスよりのものとしては、フィットネスクラブマネジメント技能検定があります(この1級は国家資格)。ページ33
学校体育で呼吸法、ストレッチ、ウォーキング、基本の筋トレーニング、ヨガなども学んでいたり、保健の授業を立ちながら受けて、座り続けることが健康にどのような影響を及ぼすかを学んだりすれば、体を動かすことに対しての肯定感がより高くなると考えます。ページ42
運動が大切なのはわかっているけれど、それを実行に移してないという事は、体を動かして健康になることの優先順位が低いのです。行動に移せない、移さない1つの理由になります。ページ48
…なぜ運動しないのか。その理由には3つ考えられます1つは、動かないことによるこれらの弊害が急性でなく、ゆっくりと体を蝕んでいくためにそこまで気にならないし気づけないことです。2つ目は前に触れたように運動は辛いものと言う認識があることです。… 3つ目は、自分で無意識に運動のハードルを上げていることです。ページ56
関節可動域をいっぱい使うこと、移動すること。この2つの要素を取り入れていれば、健康づくりの観点から見た「動く)」「(体を動かす」が実現できていると考えましょう。ページ58
どうやら軽い睡眠不足状態が続いていると体が不調を表さなくなり、その状態が普通だと感じてしまうようなのです。何も用事がない休みの日にいつもより多く寝てしまうようであれば、それは日常的に睡眠不足の状態だと言うことです。ページ72
これまで全く体を動かしたり運動することを意識してこなかった人は、ちょっと自分を甘やかしているかな?と言う程度から始めます。これまでゼロだったわけで、やらないよりはずっとマシなのですから。ページ81
趣味になっている人はさておき、何とか健康づくりの運動を生活に取り入れたいと考えている人には、着替えなくてよくて、汗が出るほどではない程度の運動をお勧めします。ページ83
仕事がある日は…余裕がなくて休みの日にゆっくりできる。これまで当たり前だったことのような考え方が、睡眠を主軸とすると変わる可能性があります。何かを捨てないと、新たな睡眠による恩恵は入ってきません。睡眠を戦略的に確保すること、それに付随して日常を再設計することで、仕事がある比と休みの日の差が少なくなり、どちらも活力のある1日にグレードアップするでしょう。ページ107
フィットネスを攻めの行動体力と守りの防衛体力に分類すると、体を動かす事はその両方に効果があるのですが、大前提として続けなければ効果が出ないし失われると言うことです。一度フィットネスを獲得しても放っておけば元に戻り、場合によっては最初よりも悪くなります。ページ134
運動の肝である血流促進。常に大切だと言う事は理解されていると思います。血流促進のための代表的な運動は有酸素運動です。ウォーキングは最も気軽にできると思います。歩ける人であれば、ウォーキングは辛いから無理とは言わないのではないでしょうか。ページ138
下半身の筋肉を刺激する方法で1番簡単なのはスクワットです。膝と股関節を折り曲げてしゃがみ戻ってくる動作ですが、バリエーションは豊かです。もちろん刺激程度であれば、体重以上の重りを持つ必要はありません。ページ141
その他のスタッフやマネジメント層、経営層はどうでしょうか。「健康づくりしていますか?」と言う問いに対して簡単に「もちろん!」と答えられる人は少ないかもしれません。健康づくりの場をビジネスとして提供している人たちは、必ずしも自分の健康づくりとビジネスを同じで土俵で見られているとは限らないのです。ページ148
口を使うのは食べる時と話すときだけ。話す時も息をするときは鼻から。このくらい鼻呼吸を徹底するとじわじわと生活の質が上がります。日常で鼻呼吸、歩いても走っても鼻呼吸、筋トレーニングしても鼻呼吸、いつも鼻呼吸です。ページ149
必死の仕事を始め含めて体の外からの汚れがあまり多くないので、湯船につかるだけで体を全く洗いません。シャワーだけの場合でも同じく肌をこすりもしません。また髪もシャワーで流しだけです。これを初めてから、運動で汗をかいても洗浄剤を使っていた頃と比べて格段に匂わなくなり、肌荒れや乾燥もなくなりました…遊び半分で試してみるのをお勧めします。ページ152
面倒だとは思いますが、現状把握のつもりで1分だけ呼吸を数えてみてください。もし20回を超えていたら呼吸過多といって、本来よりも呼吸が多くなっています。呼吸は少ない方が良いと覚えておいてください。ページ154
くゆっくり深く、…鼻のみで呼吸をする時間を作りましょう。ページ158」