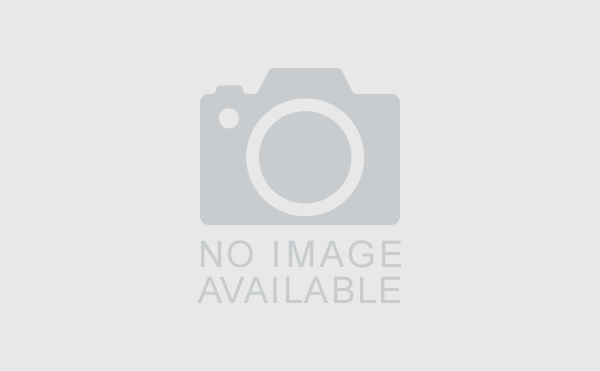「未来をつくる教育ESD」を読みました。教科書なので面白くないです。網羅的で、知識を与えるための本です。反論の余地が少ない秀才の書いた「まとめ」です。備忘します。

- 作者:五島 敦子
- 発売日: 2010/02/25
- メディア: 単行本
オルタナティブと言う言葉には、「何かにとって変わるもの」「選択可能な2つのうちの片方」といった意味があります。…この言葉ある社会の中で主流となっている習慣や方法とは異なる、別のあり方をさした際に用いられます。ページ54
共通する特徴は、第一に伝統的、画一的な教育方法に代わるものであること、第二に教育制度の多様化を目指す試みであることと言うことになるでしょう。ページ55
オルタナティブ教育は、昨日の肥大化した近代学校と言う教育のメインストリームに対峙し、子供の学習の自由及び学習選択の自由を追求する教育運動として展開されてきました。オルタナティブ教育は教育界において常にマイノリティーであり、ほとんどの国で全体の1割程度を占めるにとどまるとされます。ページ68
生涯教育から生涯学習へと表現を変えて展開されていくのは、1984年に接された臨時教育審議会が「生涯学習体系の意向」という方針を示してからのことでした。ページ85
グローバリゼーションが席巻する今日、このような状況は多かれ少なかれ、各国で見られるのではないでしょうか。日本も例外ではなく、グローバル経済の波が押し寄せ、若者は単純労働市場に駆り立てられるものと、ITなど高度な技能が求められるニューエコノミーに分断され、両者の経済格差はもとより、希望格差までも歴然としてきているのが現代の日本社会です。ページ103
イギリスの子供学校家庭省による全国のすべての学校をサスティナブルにすることを目指す運動では、持続可能な開発に不可欠な概念として「ケア」が挙げられ、3つの「ケア」を学校教育で大切にしていくこと、すべての学校で実践されることが求められています。すなわち、自身へのケア、相互へのケア、環境へのケアです。ページ104
ESDを学業教育と同義であるとみなす立場に対して、それは環境教育以上のものであり、南北格差等を重視する開発教育の要素も同様に重要であるとする見解があります。ページ106
第二の特徴として、「つながり」への着目が挙げられます。ページ107
ESDの特徴として3番目に指摘したいのは、教育のあり方自体を問い直す性格、すなわち「教育のパラダイム転換」が求められているということです。ページ108
このように、地球温暖化、エネルギー危機、食糧危機と言う「トリプルリスク」の時代に私たちは生きています。この3つの切迫した問題に、私たち一人一人が向き合い、対処していかなければならないのです。ページ125
「システム思考」とは、一つ一つの出来事のつながりをたどり、全体像を理解して、根本的な解決策を考えるアプローチです。ページ130
一方「バックキャスティング」は「振り返る」という意味で、最初に将来の理想像(ビジョン)を描き、その目標達成するためにより効果的な方法を考え、実行するやりかたです。ページ131
「成長」について考えるとき、単に成長がいけないと否定するのではなく、「奨励すべき成長」と「抑えるべき成長」を区別することが重要です。「奨励すべき成長」とは、私たちの幸せや満足につながるような成長のこと。これは抑える必要はなく、どんどん成長させていきたいものです。一方、私たちの幸せを増やそうと言う経済活動が、大量の二酸化炭素排出量や資源エネルギー消費量を伴うのであればこれは見直す必要があります。ページ134
一方の日本では、国のレベルよりも自治体レベルで再生可能エネルギーの導入がすすんでいます。日本には、太陽光や風力、小水力、地熱、バイオマス、バイオガスなど、様々な再生可能エネルギーがあり、地域によってその土地の特性や条件に合った再生可能エネルギーを利用することが可能です。ページ139
ここでのキーワードは文化や人の多様性です。多様性(ダイバーシティー)には「多種多様な状態、また特性」と「つながり支え合っている状態」の2つの意味がありますが、社会や企業学校などの組織上においては、多様な文化的社会的背景を持つ構成員の一人ひとりが、それぞれの持てる力を発揮して活躍できる状態を指します。ページ148
社会的な問題に対して、それぞれが「私の問題」として主体的に問い直す関係は、支援活動に参加しているだけで達成できるものではありません。常に自分自身や社会のあり方を深く省みて批判的に問い直すという、難しいけれども必要なプロセスを私たち一人一人が経験していくことが不可欠です。ページ199