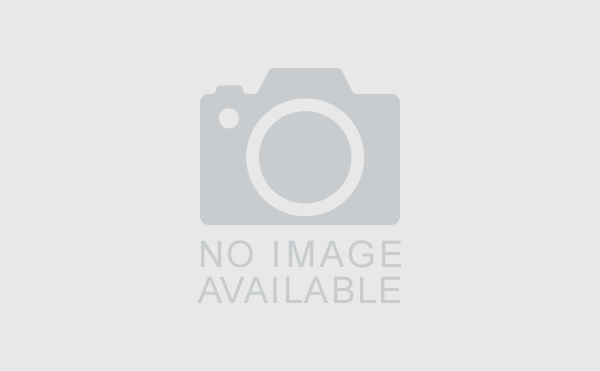本日、池田先生の「イノベーションの法則の講義を聞きました。
孫正義氏の「光の道」構想の誤りと、スティーブンジョブスがアドビのflash拒否の話から始まりました。イノベーションの話では定番のクリステンセン「イノベーションのジレンマ」の説明のあと、アップルの成功と失敗の歴史を概説してくれました。イノベーションはほとんど成功しない博打みたいなものだが、「先入観をもたないこと」「既存のパラダイムを疑うこと」によりパラダイムを転換できたものが成功する場合もあるそうです。アップルの歴史を見ると、成功と失敗は紙一重、成功は失敗の素で、失敗も成功の素だということがよく分かりました。ギャンブラーの感覚とこだわりが大事であることも理解しました。質問に回答する中で非常に重要なことを言っていました。「クラウドは最終の形ではない、インターネットの本来のアーキテクチュアは分散である。googleのように自社のストレージに情報全部を集めるという考え方は、いつか別のイノベーターにブレークスルーされる。例えばHDレコーダーを自宅のクラウドにするとか、個人のHDの空きスペースを利用するとか…」と予言しておられました。自分の業界で適用できるか、ずっと考えながら聞いていました。はじめて知りましたが、ジョブスが尊敬しているのはソニーの盛田氏だそうです。日本人も棄てたものじゃない。備忘します。
クリステンセンは元経営者で中年になってからハーバードで学んだ。
ときどきのHDDのトップメーカーは潰れるのは何故か→お客の声をよく聞いても潰れる。お客と一緒に潰れる(DEC)
経営者はアーキテクチュアの変化に対し、どのように動くかのセンスが重要だ。
アップルはソフトを売りたいのであって、ハードはタダで配っても良いと思っている。
FLASHを拒否するのはプラットフォーム戦争だからだ。IBM→MICROSOFT→GOOGLEマイクロソフトは終わった。MICROSOFT→APPLEかもしれない。
プラットフォームを支配することが最優先。ビルゲイツは初めは、オープンで。ゆっくりとクローズして大儲けした。
天動説→地動説の話。
先入観を持たないこと、既存のパラダイムを疑うことからイノベーションは生まれる。
アップルの歴史。1984のマッキントッシュのコマーシャルフィルムは傑作だ(実際にyoutubeで見た)。ジョージオーウェルを題材。
85年にビルゲイツがジョブズに手紙を書いた。OSをライセンスするようにと。ここでライセンス販売すればもしかしたらマイクロソフトはアップルだったかもしれない。
経営者の戦略的失敗があった。経営者の間違いであった。
ジョブスはギャンブラーのセンスとこだわりを持っていた。
日本の会社はコンセプト不足、こだわり不足である。
ジョブスの原点はソニーであり、iPodはソニーの模倣に過ぎない。あるプレゼンの最初に盛田氏の追悼選説を行った。
良いモノを安く売るというような製造業的な考えでは勝てない。
ピアtoピアは日本では犯罪者扱いだが、ネットの基本的な考え方だ。
ストレージそのものを共有する仕組みが面白いのではないか。
クラウドが最終形ではない。次のブレークスルーは分散にあり。