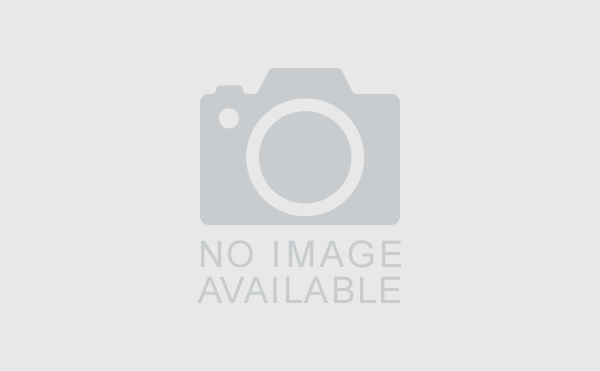「エコノミストは信用できるか」(東谷暁著 文春新書刊)を読みました。今から7年ほど前の本で、バブルの崩壊やその後の経済政策に対する発言の評価を記した本です。なかなか面白い本でした。この本を読むことによって、これまではっきりと解らなかったケインズの経済学と新古典派の経済学の差異や、インフレターゲット論の意味を理解できました。また「エコノミストの意見はよく変わる」「エコノミストの意見は米国の流行に大きく影響されている」ことを知りました。それにしても7年間、堂々巡りの議論を繰り返しているのに驚きました。
「パチンコ・カラオケ・麻雀はやめなさい」の長谷川慶太郎氏の凋落、「電車内痴漢事件」の植草一秀氏の高い評価、「証拠隠滅」の木村剛氏の正論(暴論)、「ミスター円」の榊原英資氏の世渡り、「小泉純一郎」の竹中平蔵氏のまともさ、「超」の野口悠紀夫氏のこだわり、「池田先生にバカにされていた」森永卓郎氏の単純さ、「経済同友会」の山口義行氏の活動などなど、かなり楽しめました。ちなみに99年の評価一位は原田和明氏、01年度は池尾和人氏でした。
民主党政権下、現在も経済政策論争が続いています。無責任なエコノミストに破れかぶれの政策を吹き込まれないよう神に祈りましょう。備忘します。

- 作者: 東谷暁
- 出版社/メーカー: 文藝春秋
- 発売日: 2003/11/20
- メディア: 新書
- 購入: 1人 クリック: 31回
- この商品を含むブログ (22件) を見る
本書が対象とするのは、この「もっともらしい解釈をみつけ」る、マスコミとエコノミストが作り出す喧しい声のほう。つまり、「市場の声」ではなく「声の市場」なのである。(p.13)
基本的に国債の評価が何によってなされるかといえば、その国の「経済」ではなく、その国の「政府」の信頼性にほかならない。(p.86)
いまも、森永卓郎氏のようなシンプルな金融緩和論者は、もっと思い切った量的緩和をすれば、「すぐにでも不況から脱出できていた」と論じる。しかし98年の時点で、実は、すでにかなりの金融緩和が、日銀によって実施されていた。(p,108)
…小泉首相は竹中大臣に丸投げ、竹中大臣は木村氏に丸投げというのが現実だった。…りそなホールディングスへの公的資金注入が発表されたとき、これは「失政」だとか、「予想外」の出来事だとかいう論評もあったが、木村原案を見る限り予想外の事態ではなく、まさに、こうした事態を目指すプランだったことがわかる。ただし、木村原案にあった、財政政策と金融政策がフル活動していないことを除いては−(p.193)