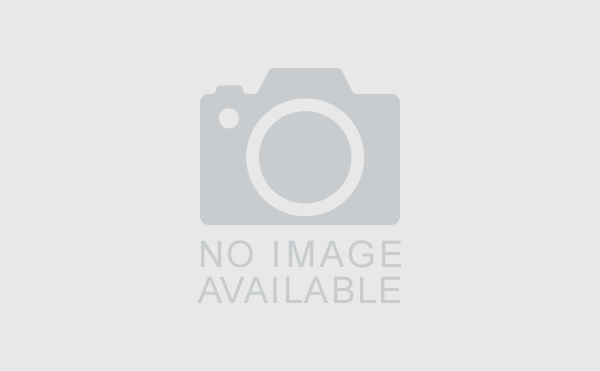「古代翡翠文化の謎を探る」を読みました。以前、糸魚川を訪れた際に、糸魚川ミュージアムで購入しました。「古事記を旅する」によればヒスイは我が国の糸魚川の産出であり、この地で加工され、日本全国に持ち込まれたそうです。しかし、古墳時代の末期には廃れ、千年以上忘れ去られていました。20世紀半ばの戦後になり、この地がヒスイの生産地であることが再認知されたそうです。古墳から出土する勾玉はヒスイでできており、胎児のかたちをしている。この宝石は、輸入品である」と記憶していました。しかし勾玉は胎児のかたちを模したものではなく、タツノオトシゴのような海からの贈り物(海産物)のかたちではないのか? 堅くて加工しづらい石をあえて装飾品にしたのは、永遠を求めた縄文人の心ではなかったか?興味は尽きません。★

- 作者: 小林達雄
- 出版社/メーカー: 学生社
- 発売日: 2006/03
- メディア: 単行本
- クリック: 15回
- この商品を含むブログ (2件) を見る