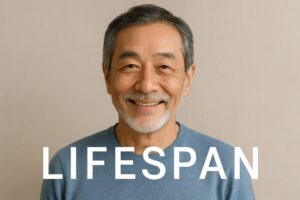テレビからしばらく姿を消していた「ブラタモリ」が再開された。画面越しにタモリを見て、ふと「まるくなったな」と感じた。でも、あの“毒”が抜けたように見えるのは、社会が“ホワイト化”したせいなのか、それとも本人が変わったのか?──そんな思いを抱えて『タモリ学』を読んだ。
読み終えてわかったのは、タモリの本質はまったく変わっていないということ。そして、私が以前から感じていた「タモリは“ブラタモリのタモリ”を演じているのでは?」という印象が、この本によって確信に変わった。
“精神は自由であり、不安でもある”
タモリはキルケゴールの言葉を引き、「人間とは精神である。精神とは自由である。自由とは不安である」と語る。自分で選び、否定し、決定する──だからこそ人間であり、そこには不安がつきまとう。それでもなお、そう生きるのが“自由”なのだ。
鶴瓶が「セオリーを崩して新たな一面を引き出す芸人」と評したように、タモリの芸風は予定調和を壊し、即興性を楽しむ“ジャズ的”なもの。何が起きるかわからない瞬間に身をゆだね、面白さを引き出す。そういう姿勢が、時代を超えて魅力を放ち続けている。
赤塚不二夫への弔辞──“これでいいのだ”に込められた哲学
本書のなかで最も心を動かされたのが、赤塚不二夫の告別式でタモリが読んだ弔辞だった。
「…あなたの考えは、すべての出来事、存在をあるがままに、前向きに肯定し、受け入れることです。(中略)この考えをあなたは見事に一言で言い表しています。すなわち『これでいいのだ』と。」
この言葉の奥にあるのは、単なるギャグではない。“意味”や“正しさ”から解放されて生きる自由への祈りだ。何があっても肯定し、笑いに変えるその哲学にこそ、タモリという人間の核心がある。
言葉をやっつける──意味に縛られない思考
松岡正剛との対談で語られた「言葉をやっつけようという気がある」という一節も興味深かった。言葉があるせいで、本質が見えなくなる感覚。文化は言葉でできている。でも、それは同時に枠でもある。
意味から自由になるために言葉を使う──それが、タモリの芸の一面なのだ。
「感動しない」「夢を語らない」という反骨
「感動したりする人間が嫌い」と語るタモリの姿勢も印象的だった。なぜなら、「カワイイ」と何にでも言うことで自分を演出する人と同じように、「感動している自分って素敵でしょ」と言いたいだけだから。
「夢なんて語らない。夢があるから絶望があるんだ」とも語る。これほど徹底した“逆張り”のようでいて、どこか深い共感を呼ぶのは、その裏にある覚悟と優しさがにじみ出ているからかもしれない。
まとめ──「これでいいのだ」という軽やかな覚悟
本書を通して浮かび上がるのは、悲観も楽観もせず、「今ここ」を受け入れて自由に生きるタモリの姿だ。どんなものも面白がり、楽しむためには、実は深い知性と訓練が必要だということを、私たちはタモリから学べる。
そして、あらためて思う。やっぱりタモリはすごい。そのスタンス、その視点、その哲学。どれもが、軽やかに、でも確かに、私たちの心に風を通してくれる。
「これでいいのだ」──今、その言葉が前より少しだけ深く響いてくる。
それは何より子供時代の自分自身が、大人たちの欺瞞を見透かしていたと言う記憶があるからではないだろうか。18 タモリはできレースも許さない。ページ22 そしてタモリは「人間とは精神である。精神とは自由である。自由とは不安である」というキルケゴールの言葉を引用し、それを解説していく。自分で何かを否定し、決定し、…人間であり、それが自由であるとすればそこには不安が伴う。ページ25 鶴瓶は、タモリを「受け答える芸人じゃなくて、相手を俯瞰してものを言う芸人、セオリーを崩して、新たな一面を引き出す。これまでにない形の芸人だ」と表する。ページ40 俺の人生の扉、ドアはあのホテルのドアだった、あれを開けると開けないじゃ、人生は変わっていたこ。の出会いの衝撃を受けた山下洋輔は新宿ゴールデン街のバー「ジャックと豆の木」などでことあるごとに「九州に森田というすごい面白い奴がいる」と宣伝し、やがてバーのママの発案で、伝説の九州の男、森田を呼ぶ会が常連客により結成された。ページ51 タモリについて芸そのものがジャズ的と作家の高野は分析している。「」ジャズと同じように繰り返しと、偶然性を持っている。そこに面白さが出ている出てくると。ページ57
【備忘】
赤塚不二夫の告別式で、タモリは森田一義として弔辞を読み上げた。冠婚葬祭を祝うタモリが62歳にして初めての弔辞が、赤塚不二夫に向けてのものだ。…「あなたの考えは、すべての出来事、存在をあるがままに、前向きに肯定し、受け入れることです。それによって人間は意味の世界から解放され、軽やかになり、また時間は前後関係を立ち放たれて、その時その場が異様に明るく感じられます。この考えをあなたは見事に一言で言わらしています。すなわち「これでいいのだ」と。ページ59 タモリと松岡は80年3月3日に長時間の対談を行い、それは「愛の傾向と対策」として書籍にまとめられた。タモリはこれを珍しい対談だった、忘れられない対談だったと振り返っている。「言語というものに復讐戦をしたくなるという松岡にタモリは同意する。「言葉をやっつけようという気がありますね。言葉を使ってね、言葉と、まず意味でしょ、その辺からやっつけて。意味をなくそうってね」ページ103 簡単に言えば理由は言葉に苦しめられたということでしょう。何かものを見て、言葉にした時は、もう知りたいものから離れている、言葉があるからよくものが見えないということがある。文化と言うものは言葉でしょう。気持ちというより言葉です。ものを知るには、言葉でしかないと言うことを何とか打開せんといかんと使命に燃えましてね。ページ106 女性がもともと喋りたいものなのに、その機会を認めなければモテなくて当然だ。また男は女性から相談されると何とか解決策を見出そうと考える。しかし、真摯に答えを出せば話すほど女性は不満に感じるのだ、とタモリは指摘する。女性は解決しようと思って相談してるわけじゃない。喋りたいからその全部喋ろうと思ってるわけね、だから女性との会話に対してノーとかイエスとかはないんだ。イエスしかない。ページ158 我々のテレビ番組に対しても、すぐ低俗でばかばかしい下品だと決めつけるのは、知性のない証拠。馬鹿なものにある、解放的というか、日常からはみ出た特性という得体の知れない力を楽しむ、これは知性がなければできない。どんなものでも面白がり、どんなものでも楽しめる、これには知性が絶対必要だと、タモリは言う。ページ199 別の場でタモリは、「私は大体感動したり、感激したりする人間が嫌いなんですよ」と語っている。なぜなら、あれは何でもかんでもカワイイと言っている女の子が、そうすることで自分の可愛さをアピールしてるのと同じで、感動している俺っていうのは、人間的に素晴らしいだろうといってるようなものだと。そして感動する人間というのは、感動がなくなっていくと思うと。そしてその話題に続けて、夢なんか語らないんだと。夢があるから絶望があるわけですからと語っている。ページ226 様々な紆余曲折を経た上で悲観も楽観もせず「これでいいのだ」とありのままに受け入れ、自由に生きる。それこそがタモリをタモリたらしめているのだ。その現在にしか希望はないのだ。ページ230