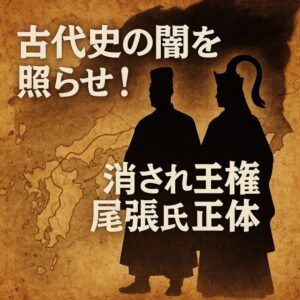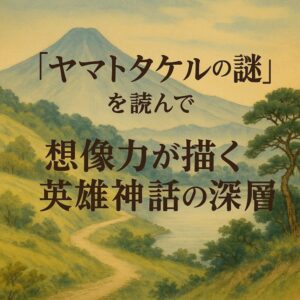中村隆之氏の『一冊でつかむ日本史』を読みました。コンパクトに日本史を通観できる点は、新書として非常に優れており、特に日本精神や神道を軸にまとめられた構成は、他の歴史概説書にはない視点がありました。
ただ、著者が語る「歴史哲学」の部分については、正直私にはしっくりこない部分もありました。同世代の著者ながらも、ものの捉え方や価値観には隔たりを感じます。人類史の進歩を信じる歴史哲学的楽観にも少し距離を置きたくなります。
神道と日本の統治の変遷
本書では、10世紀に「家」という単位が形成され、血縁集団の集落が崩壊していった過程が丁寧に描かれていました。特に印象的だったのは、地方豪族のまつっていた神々(スサノオや大国主命)から、中央の分社(八幡宮や天満宮)へと祭祀が移り変わる過程(p.62〜66)。これは、荘園制度の広がりと中央権力の浸透の裏付けでもあります。
また、平安期の政争は意外なほど穏やかで、「死刑ゼロ」の時代が続いたという指摘(p.71)も興味深く、現代の我々が持つ中世イメージとは異なる実像に気づかされました。
刀狩りと庶民の武装:誤解の修正
これまで私は「刀狩り」は庶民から武器を取り上げる政策だと理解していましたが、本書によるとそれは誤解だったようです。実際には武士と農民の身分を明確に分ける象徴的政策であり、庶民にも必要があれば武器所持が認められていたとのこと(p.94)。これには目から鱗が落ちました。
科学と戦争、そして責任
原爆開発をめぐる記述(p.136)も印象に残りました。政治家だけでなく、科学者にも等しく責任があるという筆者の主張には共感します。科学は人類に大きな恩恵をもたらしてきた反面、その裏に「人々に媚びるための虚像」があるかもしれない、という警鐘も重要です。
「最新の近代科学にも、常に疑いを持ちながら接すべきだ」という姿勢は、現代を生きる上で忘れてはいけない視点でしょう(p.104)。
明治維新と日本の奇跡
植民地化を免れた理由についての記述(p.114〜115)も印象深いです。日本人の教育水準の高さ、寺子屋の存在、そして「天皇の治める日本」という国民的意識の浸透――これは偶然ではなく、ある種の「必然」として捉えられていました。
薩摩や長州に肩入れしたイギリス、幕府に協力したフランスも、日本をコントロールしきれなかったという点も、日本人のしたたかさを示すエピソードです。
「日本人らしさ」とは何か
最後に、日本人の特徴として著者が挙げた次の三点(p.146)は、なるほどと思わされました。
- 神道に基づく人間中心の考えと天皇制
- 武士道という倫理観
- 外国文化への旺盛な受容力
これに加え、日本人が自然を大切にし、霊魂を持つ存在として扱ってきたこと(p.148)も、日本史を学ぶ上で忘れてはならないポイントだと思います。
おわりに:歴史を哲学するということ
著者は歴史哲学の目的を「人間の素晴らしさを再認識すること」と語ります(p.198)。人類の歴史が果たして「良い方向」に進んでいるのか――私は、そこには全面的には同意できません。ただ、「人々のために何かしたい」という思いが文明を作ってきた、という視点には励まされる思いもあります。
本書は単なる通史ではなく、歴史を通して人間や社会のあり方を考える試みでした。私とはスタンスの違いを感じつつも、学ぶことの多い一冊でした。
備忘します。
そこで、家を作れなかった者は、いずれかの家長に従ってその保護を受けざるを得なくなったのである。このようにして10世紀に国内の血縁集団からなる集落が一挙に崩れ、それに代わって家が現れた。ページ62
9世紀までの軍は、このような形で地方豪族が行う祭祀を通じた1つの共同体を構成したのである。有力な武士はこういったつながりを破るために、郡司の支配下にあった旧来の神社に代わって、中央の有力な神社の分社をまつるようになった。これが荘園制の発展につながった。ページ64
地方豪族が地域の守り神とした神や集落の神は主に、スサノウ、大国主命などの日本神話で活躍する。日本で古くからまつられた神からなる。しかし、荘園の神社には八幡神社、天満宮など平安時代に好まれた神社が多い。ページ66
この後、平治の乱の勝者である平清盛が勢力を張った。平安初期から保元の乱に至る間の貴族社会は極めて平和であった。その期間に死刑は全く行われず、政争で敗れたものは普通は地方間に左遷された後に、しばらく経って京都に呼び戻された。ページ71
鎌倉幕府や室町幕府は、朝廷の委任を受けて国政にあたる形をとっていたが、その支配は国内の隅々まで及ぶものではなかった。鎌倉幕府は独立した領域を持つ御家人たちを統率するだけのものであり、室町幕府は守護大名の連合政権に過ぎなかった。ページ93
刀狩りは、武士と農民との身分を厳密に区別するために行われた。これによって武士は、大小2本の刀をさして歩くものとされた。しかし、それは庶民の武器を取り上げるものではなかった。この時から江戸時代末までは、農民や町人も必要に応じて鉄砲を保有したり、1本の刀を身に付けて外出する権利を認められていた。ページ94
この例から現代人が真理と見ている最新の近代科学に対しても、常に疑いを持ちながら接していかなければならないことがわかってくる。科学の書物の内容は合理的に見えるが、もしかするとそれは科学者が、人々に媚びようとして作り上げた虚像であるかもしれないのだ。ページ104
鎖国と朱子学の盛行を江戸時代の日本の進歩を妨げたものと見る説もある。そういった見方も可能だが、朱子学者が日本に合理的思考を広め、支配層に善政を薦め、庶民の教化に尽くした点も見落とせない。ページ104
幕末の政治の混乱を、「日本を植民地化する好機」ととらえた欧米人もいただろう。しかし日本は植民地化されなかった。その理由は次の2点に求められる。1つは日本の諸勢力が「日本人」としての強い団結力を持っていたこと。そしてもう一つは、日本の学問や教育の水準が高かったことであろうある。…日本の庶民が、寺子屋の教育の中で書物を読み自らの頭で考えたうえで、「自分たちは天皇の治める日本の一員だ」とする信念をもっていたからだ。ページ114
…倒幕派の薩摩藩、長州藩についたイギリスも、幕府についたフランスも、幕末の戦争の時に武器の輸出などで大儲けをした。しかし、彼らは一方の政治勢力を思い通りに操る事はできなかった。ページ115
廃刀令は、このような形で武士の誇りを失わせるものであった。廃刀令に伴う形で特別の例外を除いて庶民の持つ鉄砲や刀も取り上げられた。政府の側の人間である軍人と警官以外の者の武装が許されない時代になったのである。ページ118
ドイツでは化学工業、医薬品などの分野の新技術が生み出され、イギリスやフランスでは独自の科学を踏まえた産業が発展した。ところが大正時代に入った頃から日本人の優秀な科学者が減少していった。ページ123
物理学が一般常識で理解可能であった量子論以前の時代の政治家は、自ら科学思想を学び政策を立案することができた。しかし科学者や技術者の世界が外の者に近づきがたいものになってしまうと、政治家は科学技術の分野に関して専門家集団の言いなりになるほかない。彼らの立場は、陰陽五行説に基づく陰陽師の裏に従って行動した平安貴族と変わらないのではないか。原爆を落とした責任は、それを命じた政治家が負うべきものであろうか、原爆を作った科学者が追うべきものであろうか。筆者は両方悪いと思う。ページ136
しかし第二次世界大戦の死者の数を記した表を見て欲しい。勝者である連合軍側の死者が、敗者である枢軸国側の死者の5倍に達している。これは一見不可解な数字である…ゆえに先に手を出した側が悪いのである。私たちはこの点を見落としてはならない。ページ119
そこで先進諸国は1985年に会議を開いて日本には圧力をかけ、円高に導くことによって日本の輸出を減らし輸入を増やすことを決めた。この決定をプラザ合意という。これによって円高となり世界中の投資家が日本経済は強いと考えて日本に資金を継ぎ込んできた。そのため、1986年頃から日本の土地や株が急騰し、バブル経済と呼ばれる好況が訪れた。ページ132
ここからそこに住む日本人の特徴について考えていこう。…
①神道に基づく人間中心の考えを取り、それに基づいて天皇星を作り、それを継承してきたこと。
②武士としての道徳(武士道)を重んじること。
③海外の先進文化に強い興味を持ち、それを貪欲に取り込むこと。
つまり「日本は世界のあらゆる文化が取り込まれる、天皇制の元のサムライの国である」ということになる。この特徴は今日の日本にも当てはまるものである。ページ146
「一人ひとりの人間はかけがえのない霊魂を持つ大切なものだ」「動物も植物も川の水や山の岩石などの自然物は各々、霊魂を持ち神様に守られたものだから粗末に扱ってはならない」そして日本人は他人の気持ちを尊重し、人命を大切にする社会を作ってきた。そして日本では近代に至るまで大掛かりな自然破壊が行われずにきた。日本史を理解する上でこの点は見落とせない。ページ148
歴史を知ることによって、人間の素晴らしさを再認識する歴史哲学は様々な手法があるが、私の歴史哲学の目的は、「歴史を知ることによって、人間の素晴らしさを再認識する」ことにある。様々な揺れはあっても人類の生活がより豊かで快適な方向に向かっている。人間が何も考えずに生きてきたならば人類の進歩はなかった。人々のために何かしたいという多くの人の思いが文明を発展させてきた。ページ198