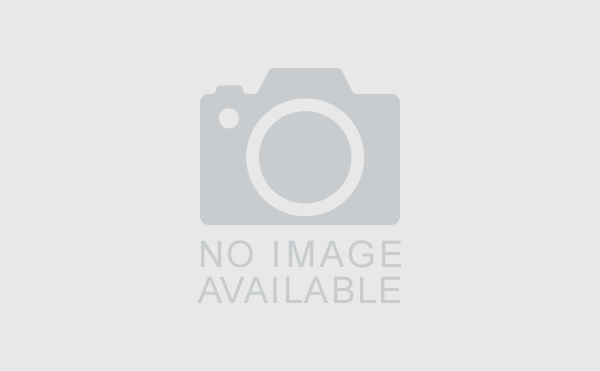はじめに
先日、黒滝先生(東京農業大学教授)の著書『榎本武揚と明治維新』を読みました。私は函館に住んでいたことがあり、五稜郭や碧血碑にも足を運んだ経験があります。函館検定の勉強もしていたので、榎本武揚(書名では「武明」となっていますが、一般には「武揚」で知られています)についてはある程度知識があるつもりでした。しかし、本書を読んで「自分はまだまだ知っているようで知らなかったな」と痛感するとともに、榎本の功績と人柄の奥深さに改めて感銘を受けました。
中島三郎助の逸話と、榎本武揚への誤解
函館戦争の降伏直前に、中島三郎助という旧幕臣が親子で亡くなったことは知っていましたが、その後榎本が「ご遺族に申し訳ない」と感じ、残された三男を海外留学まで支援して海軍中将にまで登りつめた、というエピソードは本書を読むまで知りませんでした。
以前は「二君に仕えた」「旧幕府を見捨てて逃げ延びた」など、榎本に対して否定的なイメージを抱いていましたが、実は“国に仕えた”人だったのだと理解できたのは大きな収穫です。
本書の中でも、榎本が「旧幕臣の仲間が困っていたら助けてほしい」と家族に度々手紙を送っていたエピソードが紹介されています。かつて抱いていた“出世主義者”という印象は、少なくとも表面的なものであったと感じます。
ガルトネル林の租借計画と大きな失敗
榎本の近代化政策や開発のビジョンが大きく転換していったきっかけとして、ドイツ人のガルトネルやブラントに対して七重村(現在の七飯町)の300万坪を99年間貸与し、外資による開発を進めようとしたという史実が紹介されています。当時のヨーロッパと同じような気候を持つ蝦夷地を見て「植民地化の機会を狙っていた」とも言われますが、榎本自身も後に「大きな失敗だった」と認識するようになったようです(p.8)。

実際、私も七飯へ足を運んだ際に“ガルトネル林”と呼ばれる場所を見学したことがあります。そこで果樹園をはじめ、今も立派な農業が展開されている様子を目にし、「榎本が残したものの名残」という歴史の奥行きを感じました。
榎本武揚の「万能人」としての才能
本書を読んで最も驚いたのは、榎本武揚が近代化全般の知識と技術、そして国際法を学び、政治・外交・産業・教育など多岐にわたって貢献していたという事実です。五稜郭の戦いの後、新政府に囚われのみとなったにもかかわらず、重要ポストを歴任できたのは、オランダ留学で身につけた先端技術や国際感覚を評価されたからだといいます(p.38)。
「結局オランダ留学は27歳から32歳までの1862年から1867年の5年間となった。…鉱物学、機械工学、冶金学、電信技術、…さらに国際法を重点的に学び、近代日本の万能人の評価をなす基礎を形成したと言える。」(p.15)
この引用の通り、榎本は留学中に多分野の知識を吸収し、それを明治新政府に生かしていきました。
函館戦争と「生き恥を晒してまで生き延びた」真相
函館戦争をめぐっては、土方歳三が華々しく散った英雄として語られる一方で、「生き延びた榎本」は否定的な見方をされることが少なくありません。本書では、榎本が降伏を決意した際に切腹まで覚悟したものの、家臣たちに止められたというエピソードが紹介されています(p.55)。

「五稜郭を解除して死を選ぼうと覚悟し、…短刀を手に腹につき立てようとするが、大塚が手づかみでそれを奪い取り、…榎本は切腹を思いとどまることができた。」

このとき右手の指3本を切ってしまった大塚に対して、榎本は生涯気遣い、面倒を見続けたとも言います。本書を通して、榎本が見せた“仲間への思い”や“義理を重んじる人柄”が伝わってきました。
北海道開拓への大きな貢献
榎本は北海道開拓の先駆けとして、その功績は多岐にわたります。例えば、
・炭鉱の発見
・函館海底ケーブルの日本人による敷設
・東京農業大学の設立と教育への貢献
・殖産興業を支える地質調査への寄与(1876年5月10日に日本で最初の本格的地質図を発表したライマンの活動に参考情報を提供している)
さらには1922年、有島武郎が小作人に土地を無償開放する以前に、榎本自身が1919年に9人の小作人に土地所有権を移転したことも記されていて(p.78)、まさしく先進的な「小作解放」を実践していたのだとわかりました。
「北海道では1922年に作家の有島武郎が現在のニセコ町の農場を小作人に無償開放したことが有名になったが、実は榎本はそれよりも先んじて1919年に9人の小作人に土地所有権を移転して小作開放を行ったのである。」(p.78)
こうしたエピソードを見ると、榎本が単なる「官僚」や「政治家」ではなく、現場に寄り添う実践家であり、かつ教育者としても力を注いでいたことがよくわかります。
外交と国際法による平和的な国境画定
榎本武揚の最も評価されるべき功績の一つが、ロシアとの樺太・千島交換条約を締結し(p.84)、さらに清国との日清間紛争を解決へ導く天津条約(p.88)にまでつながる交渉を行った外交手腕です。
「さらに重要な事は榎本は戦争によらず平和に国際法の外交交渉を通じた国境線の確定や紛争の解決を目指したと評価されることである。函館戦争での近代戦の悲惨さも脳裏にあったものと思われる。」(p.90)
函館戦争をはじめとする国内の争いを身をもって体験したからこそ、「もう二度と悲惨な戦いを繰り返してはいけない」という思いで外交に臨んだのではないでしょうか。
碧血碑への想い
1907年、72歳になった榎本は体調が少し回復すると、わざわざ函館山の中腹にある碧血碑を訪問しています(p.160)。この碑は、函館戦争で亡くなった旧幕府軍の兵士を弔うために建てられたもので、彼らの遺体を収容した侠客の柳川や、募金を募った榎本の人柄が見えてくる史跡です。
私も碧血碑に行ったことがありますが、当時はただ「旧幕臣の慰霊碑」くらいの認識でした。しかし本書を読んだ後では、そこに込められた榎本の複雑な思い、そして“義”を大切にする精神をより強く感じます。

明治維新と旧幕臣の活躍
私たちはよく「明治維新=薩長土肥がつくり上げた」とイメージしがちです。しかし著者は、実は旧幕臣をはじめとした多くの人々が近代化を支え続けたと強調しています(p.167)。榎本武揚はその象徴といっても過言ではない存在なのです。
おわりに 〜「万能人」の志を現代へ〜
過去に函館で暮らしていた者として、榎本武揚について「もっと知っておけばよかった」と感じています。函館検定の勉強でそれなりに知識は身につけたつもりでしたが、本書を通して彼の多彩な活躍と人間味あふれる一面に触れ、まだまだ理解が浅かったことを痛感しました。
「以上榎本武の生涯を見てきたが、フロンティアスピリットを持って、あらゆる科学に接し、北海道の開拓や殖産興業に大きく貢献してきた榎本の人生はまさに近代日本の万能人であったといえる。(中略)…現代の社会問題に立ち向かう際、継承すべきなのは、1.国際交流の視点、2.持続的な社会発展の視点、3.地域資源とものづくりの視点、4.近代科学を前提にした教育者としての視点、5.文理融合の万能人・総合人としての視点であると言えよう。」(p.168)
この言葉を胸に、“国に仕え”、地域に寄り添い、国際社会と積極的に関わった榎本武揚の姿勢を、今を生きる私たちも見習っていきたいと思います。函館にゆかりのある方、あるいは北海道の開拓史や明治維新の裏側を深く知りたい方には、ぜひこの本を手に取ってみることをおすすめします。きっと「近代日本の底力」を感じられるはずです。
函館には五稜郭だけでなく碧血碑や旧幕府軍ゆかりの地が数多く残っています。市民や観光客の方にこそ、榎本武揚が果たした功績を再発見し、函館の歴史がもつ奥深いドラマに思いを馳せてもらえれば嬉しいです。私自身も、これからは榎本に対する理解をさらに深め、折に触れてその足跡をたどってみたいと思います。
(引用文献)
黒滝先生(東京農業大学教授)著『榎本武揚と明治維新』
備忘します。
榎本の近代化政策と開発方式の認識が大きく展開したのは共和国成立時にドイツのガルトネル、ブラントによる七重村、現在の七飯町の当時3,000,000坪の99年間の租借権与えた外資導入による開発計画の実現である。蝦夷地はプロイセンの気候風土にいるとして植民地化の契機を狙っていたとされる。しかしその後、榎本は大きな失敗と認識されたものと考える。ページ8
結局オランダ留学は27歳から32歳までの1862年から1867年の5年間となった。この間、榎本は、エンジニアリングの基礎としてし、蒸気機関管とともに、鉱物学、機械工学、冶金学、電信技術、さらにエンジニアとしても国際法を重点的に学び、近代化の基礎近代科学技術全般の体系として、加えて国際的秩序の体系を国際法から学んだ事は、加藤義一の近代日本の万能人の評価をなす基礎を形成したと言える。ページ15
榎本が函館戦争後、囚われのみとなったにもかかわらず、罪一等を減じられ、旧幕臣の身でありながら明治新政府の重要ポストを歴任することができたのは、こうした近代ヨーロッパの先端技術や国際法を熟知し、当時の国際感覚に明るい才能を認められたところにある。ページ38
この時榎本武昌がオランダ語で友人宛に、冒険は最良の友である、という言葉を贈っている。この言葉はオランダ留学の充実した成果を読み取ることができるとともに、これは好奇心、冒険心を持って探求をすることの重要性を体現している。ページ39
榎本は江差侵攻支援するとともに海から攻撃するために開陽丸を投入するが、この航海が旧幕府軍の命運を左右することになる。11月15日の夜、天候の急変により開陽丸が流され、江差沖にて座礁したのである。ページ52
降伏を決意した榎本は五稜郭を解除して死を選ぼうと覚悟し、総裁室にて切腹しようと軍服の前のボタンを外して短刀を手に腹につき立てようとするが、寝室で異変に気づいた大塚がここで死ぬべきではない、と短刀を手でつかんでそれを奪取した。榎本は右手の指が3本切れて血まみれになった大塚の手を見て我に帰り、その騒ぎを聞いて駆けつけた大島たちに短刀を奪い取られてようやく切腹を思いとどまるに至った。世間一般では土方は箱館戦争最後まで戦った、華々しく散った英雄として評価され、反対に榎本は生き恥を晒してまで生き延びた人物と否定的に捉えられることがよくあるが、その背景にはこうしたエピソードが存在するのである。ページ55
1876年5月10日に日本で最初の本格的な地質図日本地質要約の図を出版しており2008年からはこの日が地質の日となっているが、ライマンは榎本の報告を参考にしている。その意味では日本地質学の祖、外国人ではライマンであるが、日本人では榎本と言って良いであろう。ページ69
北海道では1922年に作家の有島武夫が現在のニセコ町の農場を小作人に無償開放したことが有名になったが、実は榎本はそれよりも先んじて1919年に9人の小作人に土地所有権を移転して小作開放を行ったのである。ページ78
榎本武揚の稀なる外交能力が発揮された事柄として、1875年にロシアとのあいだで締結された樺太、千島交換条約を上げることができる。ページ84
榎本は9月に妻子を連れて清国、北京に向かい、清国との交渉に心血を注いだ。榎本は問題解決のため、外交で世界的にも高い清国の実力者、李鴻章と渡り合う話合う。李鴻章とは初対面にもかかわらず話が弾み、かんたんあい照らす仲となり、この出会いが後の日清間の紛争を解決する天津条約の締結につながっていくことにある。ページ88
さらに重要な事は榎本は戦争によらず平和に国際法の外交交渉を通じた国境線の確定や紛争の解決を目指したと評価されることである。函館戦争での近代戦の悲惨さも脳裏にあったものと思われる。ページ90
逓信大臣時代に榎本が手がけた功績の1つとして、デンマークの大北電信に委託していた国内の海底電信戦敷設工事を日本人の手で行えるようにしたことが挙げられる。函館海底電線の工事外注を取りやめることで経費の削減をもたらした。ページ91
東京農業大学北海道オホーツクキャンパスに所蔵される、学びて後に至らざるを知る、書がある。56歳の榎本がこの年に揮毫した書である、育英設立の志が伺いて誠に興味深い。榎本には北海道開拓への強い思いがあったと考えられる。ページ109
そして彼の本領は、この日本の産業革命の基本にあたる官営八幡製鉄所の創設ひいては浦賀株式会社の設立に関わって、歴史上大きな推進役を担ったということができる。ページ118
これを踏まえて最終的には八幡村に製鉄所を設立することが決定した。ページ125
これについて明治天皇の伝として、榎本、栃木県高徳中央を巡視し、つまびらかにその惨状を目撃す。来たりて辞表を立て奉る。ページ129
榎本が切腹を図った際に大塚かわ刀を手でつかみ、その時に大塚の右手の指3本の筋が切れて不自由になったと言う。榎本は生涯それを気にかけ何かと面倒を見て小樽の北辰社の支配人として迎い入れている。ロシア公使として単身赴任した時函館戦争の旧幕臣の仲間が困っていたらできるだけの面倒を見るようにと、度々家族に手紙を書いている。また中島三郎助の家族に宛てた手紙が残っており、それには三男の将来の面倒を見ると約束している。成人した三男はグラスゴー大学へ留学し、その後、海軍中将にまでなっている。ページ156
このことに思いをしたのか1907年72歳の時に体調が再び回復してきたので、函館の市を訪れ、函館山の中腹に立つ碧血碑を詣でている。この碧血碑は、1869年の函館戦争終結後、放置されていた旧幕府兵士の遺体を、侠客、柳川熊が集めて埋葬し、このことを知った榎本の募金によって1875年に建立された。ここには榎本軍として新政府軍と戦ってなくなった800名を祀っているが、碧血とは義に殉じて流した武人の血は3年経つと青色になると言う中国の故事が言うものである。ページ160
明治維新は倒幕の主体である薩長土肥火のみが作り上げたと言われてきたが、実はこの近代化には膨大が旧幕臣系の人々の参加があったからこそ、なし遂げられたのであり、表面上の薩長の国家のトップの下にはたくさんの旧幕府系を含めたテクノクラートが存在し、近代化を担い続けたのである。ページ167
以上榎本武の生涯を見てきたが、フロンティアスピリットを持って、あらゆる科学に接し、北海道の開拓や殖産興行に大きく貢献してきた榎本の人生をまさに近代日本の万能人であったと言える。その榎本の志を踏まえて、現代の社会問題に立ち向かう際、継承すべきなのは、1国際交流の視点、2持続的な社会発展の視点、3地域資源とものづくりの視点、4近代科学を前提にした教育者としての視点、5文理融合の万能人.総合人としての視点であると言えよう。ページ168