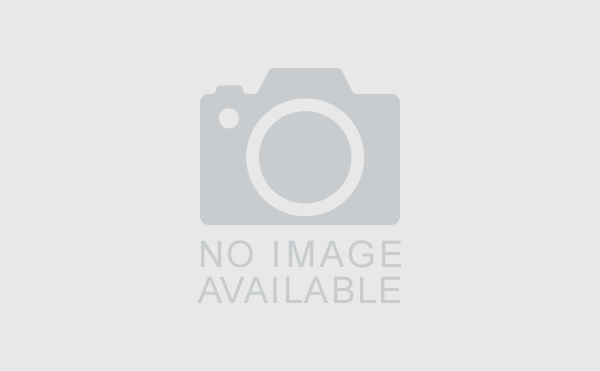「赤米のたどった道」を読みました。今、普通に食べている白米は江戸時代まで希少な品種で、赤米という味の悪い、しかし災害や寒冷に強い米を多く食べていたそうです。また「米」の伝来といってもはじめから水田を想像してはいけないのです。はじめは陸稲まじりだったそうです。つくづく今時点での先入観で語ってはいけないと思いました。古代の導入期、中世の荘園など当時の政治状況にも大きな影響を受けていることも知りました。特に江戸時代には商品作物としての米と庶民の食料としての米のせめぎ合いがあったことに驚きました。著者、福嶋紀子さんの詳細な研究に脱帽します。備忘します。

- 作者: 福嶋紀子
- 出版社/メーカー: 吉川弘文館
- 発売日: 2016/04/14
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
列島社会全域に生産の痕跡が残る赤米品種は、現在もてはやされている日本の白い米のイメージとはだいぶ異なる品種ではあるが、決してなじみのない品種ではない。実は、長い日本の稲作の歴史のなかでは、赤米が庶民の暮らしに寄り添って、生産労働のエネルギーを支えてきたと考えられる。ページ9