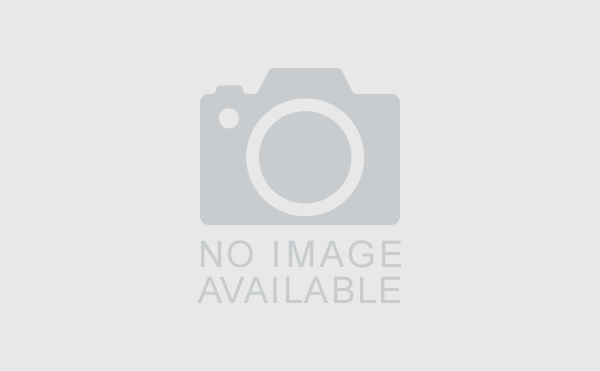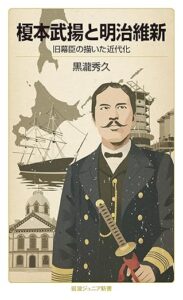/

歴史には裏がある、歴史には闇がある。本書、日本史の知られざる逸話が多数収録されている。歴史には闇がある。それを暴くことの面白さと危うさを改めて考えさせられる一冊だった。筆者の独自の見解が多く含まれているため、歴史の通説とは異なる視点で物事を見ることができる一方で、どこまでが史実でどこからが推測なのかを慎重に見極める必要があると感じた。本書の内容は、もともと新聞に連載していた記事をまとめたもののようで、「こんなこと知ってるぜ!」といった自慢話的な要素も強い。
著者は、よくテレビに出演している磯田道史氏が書いた一冊である。磯田氏は歴史マニアらしいところがあり、解説は上手だが、ややマニアックで暗い部分も多い。個人的にはあまり好みではないが、興味本位で読んでみた。
著者は京都に住み、研究所の教授を務めているようだ。趣味は古本屋巡りで、京都の数多くの古本屋を訪れ、古書や手紙を探し、それを解読することに喜びを感じている。日本史の研究者だけあって、古い筆書きの文書も読めるため、さまざまな依頼が舞い込むらしい。また、文化財の保護にも関わり、歴史的に重要な場所に道路が通る計画があると政府に掛け合い、変更を実現させるような活動もしている。
備忘します。
・明智光秀の出世
光秀は過労の松井に気に入られなかったため、逆に出世できた。松井はその返礼として、娘を細川忠興に嫁がせたという。細川藤高が光秀の才能を見抜き、信長に推薦した黒幕であった可能性が高い(P.13, 17)。
・信長と光秀の確執
宣教師フロイスの記録によると、信長は光秀が口答えしたことに激怒し、彼を足蹴にしたことがあるという(P.20)。
・本能寺の変後の毛利家の動向
毛利軍はすでに内部に多くの内通者を抱えていたため、信長の死を知っても秀吉軍を追撃する決断はできなかった。むしろ秀吉と手を組むことで、内部の敵を抱えずに済むと判断したらしい(P.29)。
・ねずみ小僧の裏の顔
ねずみ小僧は鳶職の経験があり、女子便所の屋根裏に潜み、女性の部屋を覗いていた可能性がある。彼は庶民にばら撒くために盗みを働いたとされるが、実際には遊興や賭博に消えていた(P.122)。
・最後のカリスマとその影
最後は弱者に寄り添える魅力を持ちつつも、暗殺や欺瞞を躊躇なく行う側面もあった。歴史家は、最後の影のある横顔も直視すべきだと著者は述べる(P.139)。
・明治政府の徹底した統制
明治新政府は討伐戦争を勝ち抜いた軍政国家であり、疫病対策として病院の監視だけでなく、飲酒や性行為の回数にまで制限を加えた(P.185)。
・
災害時の心理と正常性バイアス
人々は災害が起こると「そんなことはありえない」と思い込んでしまう。この心理が津波や地震の被害を拡大させる要因になっている(P.233)。