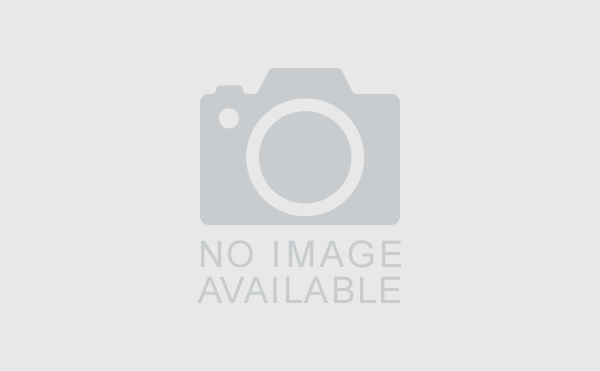小林秀雄「本居宣長」を読みました。「古事記」の理解を深めるための読書です。小林秀雄晩年の名著です。文庫本で約800ページぐらいあります。原文の引用も多く難儀しました。前半は、「万葉集」「源氏物語」を題材に宣長が「もののあはれ」をどのように体得したかの解説です。後半は、「古事記伝」の執筆の経緯と解説です。当時の学者、契沖、賀茂真淵に学び、上田秋成と論争しながら30年掛かって「古事記伝」を完成させました。
江戸時代の学者も「古事記」に書いてあるのは事実ではないとの意見が大勢でしたが、宣長は「古事記」に書いてある事は全部事実だと言い切ってます。フィクションだと考えると古代の人たちが何を考えたらわからないと言い切ってます。国学の真髄です。
私、浅学非才のエピソードを一つ。「古事記」を読むと冒頭に、神世七代が語られます。「くにのとこたちのかみ」から「いざなみのかみ」まで12柱の神が次から次へと出てきます。私は、神々が浮かんでは消えと順番に出てくると思いこんでいました。しかし、宣長によると、神様は横に並んでるって感じであるとのことでした。古代人には、神々の出現が、同時の出来事に見えていたとは! 誤読していることに気づきました。それにしても「ぼおるぺん古事記」の作者、こうの史代さんは本質を理解してます。驚きました。
宣長は「歴史を深く知ることは、人生いかに生くべきかという普遍的な課題解決になる」(
上ページ112)と述べています。知らないことが多すぎます… 備忘します。
…宣長が取り上げたのは、「もののあはれ」と言う言葉は、貫之によって発言されて以来、歌文に親しむ人々によって、長い間使われてきて、当時ではもう誰も格別な注意も払わなくなった、ごく普通の言葉だったのである。彼はこの平凡陳腐な歌語を取り上げて吟味しその含蓄する意味合いの豊かさに驚いた。上ページ127
作者は、「よき事のかぎりをとりあつめて」源氏の君を描いた、宣長言うのは、もちろん、わろき人を美化したと言う意味でもなければ、よき人を精緻に写したという意味でもない。「もののあはれ」を知る人間の像を、普通の人物評の届かないところに、詞花によって構成したことを言うのであり、この像のもつ疑いのようのない特殊な魅力の究明が、宣長の批評の出発点であり、同時に帰着点でもあった。上ページ220
…宣長が、「古事記」から直に聞いた古代の人々の音声は、まさに「耳に聞こええるままにて、その他に何もなくなきことぞ」と言う、完全な形式を取ったもので、彼はこれを極めて自然に受け入れたのだが、この簡明な経験は、同時に古人の「言問い」は、これをそっくりそのまま信じるか、全く信じないか、どちらかであるという、はっきりした意識であったことを忘れてはならない。この点では真淵の態度は、まだまだ曖昧なものであった。下59ページ
道とは何かを問われれば、自分は神代の伝説に「見えたるまま」であると答える外は無いと宣長は言う。それを読書に納得してもらうために、いやそう自分自身が納得するために、注釈を書いた…下ページ197
…もはや明瞭であろうが、宣長は、古伝説を創り、育て、信じてきた古人の心ばえを熟知しなければ、我が国の歴史を解くことは出来ぬ、神々が、伝統的心ばえのうちには、現に生きている事は、衆目の見えるところである…下ページ230
いまだ文字も知らぬ長い間の言伝えの世で、日本人は、生きた己の言語組織を、既に完成したという事実につき、宣長ほど明晰な観念を持っている学者はいなかった。そこで、古伝説は、「神の道」を主題とした物語の傑作として受け取るのが、その最も正しい読み方である… 下ページ364