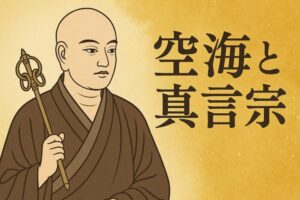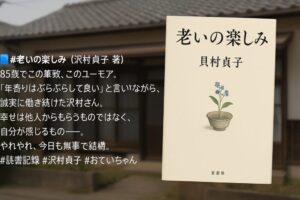全部読むつもりはなかったのですが、どうしても確認したい部分がありました。
一つは「無知の知」。もう一つは「死の定義」、つまりソクラテスの死に対する考え方です。
その部分だけを読むつもりが、やはり面白くて結局もう一度最初から再読してしまいました。改めて、奥の深さを強く感じました。読んでよかったです。
この本の著者は、どうやら研究者ではなく医師の方のようです。大学でギリシャ語を教えた経験があり、その後医師に戻られたとも記されていますが、詳しい経緯は定かではありません。精神科医としての活動経験もあったようです。
本書は原文をすべて掲載し、その後に解説と著者自身の意見が丁寧に書かれています。ソクラテスを知らない人や、『弁明』を初めて読む人にもわかるように構成されており、とても良い入門書だと思いました。
無知の知 — 「知らないことを知っている」
「私はその人よりも知恵がある。なぜなら、私たちのどちらも何も知らないが、この人は知らないのに知っていると思っている。私は知らないと思っている。この一点で、私の方が知恵があるようだ。」(p.60)
「無知の知」は哲学の根本にある態度だと改めて感じます。
自分の無知を自覚することこそ、学びの出発点であり、ソクラテスはそれを実践し続けた人でした。
中傷と嫉妬 — 変わらぬ人間の本質
「私を有罪にするのは中傷と嫉妬だ。だが、それが私のところで終わるとは思わない。」(p.110)
この言葉には、時代を超えて人間社会の変わらぬ構造が見えます。
正しいことを言う者、真実を問う者がしばしば誤解され、排除される。
それをソクラテスは皮肉とともに受け止め、真理を追い求める姿勢を貫きました。
死の定義 — 「死を恐れるのは、知らないのに知っていると思うこと」
「死を恐れるのは、死を知らないのに知っていると思っていることです。死は最大の善かもしれないのに、最大の悪だと思い込んでいる。」(p.117)
そして、彼の死に対する考えは実に深い。
「死は、夢も見ない熟睡のような静寂か、あるいは魂が他の場所へ移る旅立ちである。」(p.185–186)
ソクラテスは、死を「恐れるもの」ではなく、「どちらに転んでも善であるもの」として受け入れました。
この姿勢は宗教や時代を超えて、人間の生き方に深い示唆を与えてくれます。
おわりに
ソクラテスの思想は2500年を経た今でも、人間の根本に迫る力を持っています。
「知らないことを知る」「恐れを知に変える」——
この二つの言葉に、人としての成熟のヒントがあるように感じました。
また時を置いて、もう一度読み返したい一冊です。
備忘します。
>
…私はそこから立ち去りながら、こう考えた。私はその人よりも知恵があるなぜなら、私たちのどちらも全部の事柄は何も知らない。だが、この人は知らないのに知っていると思っているが、私は事実確かに知らないのだから知らないと思っている。だから、このちょっとしたことで、つまり知らない事は知らないと思っているという点で、私の方が知恵があるようだ。ページ60
ソクラテスは、以上の古くからの告発者と新しい国家に対する弁明をした後、自分を有罪にするのは、多くの人たちの中傷と嫉妬だと言っています。中傷と嫉妬が他の多くの良き人を有罪にし、これからも有罪にするだろうが、それが私のところで終わりになるという恐れはないと、ソクラテスは皮肉で言っているわけです。ページ110
死を恐れるというのは死を知らないのに知っていると思っていることです死死は人間にとって最大の良きものかもしれません。それなのに、最大の悪であることを知っているかのように恐れているからです。死を恐れるのは、本当は知らないのに知っていると思うという意味で無知であるということです。ページ117
しかしまた次のようにして、私が良いものであるという大きな希望があることを考えてみよう。死るという事は、次の2つのどちらかだ。全く無のようなもので、死には何についてもどんな感覚もないのか、あるいは、言い伝えにあるように、ある変化である、魂にとってこの場所から他の場所へと移り住むことであるかのどちらかである。
そして感覚が全くなく、人が寝て、夢一つさえ見ない時も眠りのようなものであれば、私は驚くほどの儲けものということになるだろう。なぜなら、もしも夢を見ないほど熟睡した夜を選び出し、自分の全人生の他の夜と昼をその夜と並べて比べて、この夜よりも楽しく生きた昼と夜が自分の生涯でどれだけあったかと言わねばならないとしたら、主に、誰か普通の人だけでなく、ペルシア大王といえども、そういう昼夜がそうでない他の昼夜に比べてごく数えられるほどわずかしかないことを発見するだろう。だから私がこのようなものであれば、儲けものだと私はいうのだ。なぜなら、全時間はこのようであれば一夜よりも少しも長くはないと見えるからだ。
しかし他方、死がここから他の場所へと旅立つようなものであり、死んだ人はすべてかしこへ行くという言い伝えが真実であれば、裁判官諸君、これよりも大きな善はあるだろうか。…他にも、その生涯において正しかった半神たちがちょうどまたかの世で裁判をしているといわれているが、このたび立ちは果たしてつまらないものだろうか。あるいはまたオルペウスやムウイオス、へシオドスやホメロスなどと一緒になることを、君たちのうちにはどんなに多くのものを差し出してもそれを受けるようとする人がいるのではないか。私はこれらのことが真実であれば、何度でも死ぬだろう。私自身にとってもそこでの暮らしは素晴らしいものになるだろう。ページ185
ソクラテスは、死が良いものという希望があることを次のように考えようと言います。主は次の二つのどちらかだよ。全く無のようなもので、死者は何一つ感覚がない状態になることか、それとも、魂がある場所からある場所に移り住むことになるかのどちらかです。前者であれば、夢一つ見ないで熟睡できた夜は、他の夜と昼とを比べると「儲けもの」だとソクラテスはいいます。…他方死がこの世からあの世に移り住むことであり、その上、あの世には本物の裁判官がいるのならこれよりも大きな善はないとそれはソクラテスは考えます。ページ186
<<