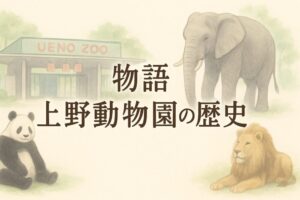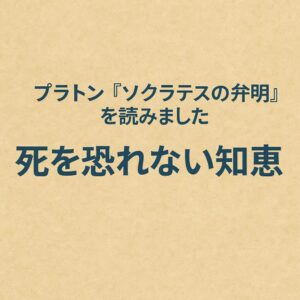「空海と真言宗-知れば知るほど」を読みました空海をまったく知らない人にも、とても良い入門書だと感じました。
彼は幼い頃から神童と呼ばれ、二十歳のころには儒教など当時の学問をすでに修めていたそうです。そして三十一歳で遣唐使として唐へ渡り、わずか一年ほどで密教の第一人者・恵果から直接教えを受け、正式に戒律を授けられて日本に戻ってきます。
この経緯がすべて史実だということに大変驚きました。まさに奇跡的な人生です。
空海は「政治に関わらない」ことを信条としていたそうですが、その姿勢がかえって権力者の信頼を集め、重用される結果となったというのも興味深い点でした。
若き日の苦悩と出家の決意
空海は大学に進学し、儒教を中心に学んでいましたが、1年ほどで中退します。
一族は落胆したことでしょう。しかし、律令国家の官吏を目指す道だけでは満たされない「何か」を感じていたのだと思われます。やがて室戸岬の御厨人洞で過酷な修行を積み、明星が口の中に飛び込んでくるという神秘的な体験を経て、真理への道を確信したと伝えられています。
恵果との出会いと密教の伝承
唐に渡った空海は、長安で恵果和尚と運命的に出会います。恵果は密教の正統を伝えるただ一人の師であり、短期間で空海に教えを授け、阿闍梨として認定しました。
このとき空海は密教の第八祖となり、「かくなる上は一刻も早く日本へ帰り、密教を広め、万民の平安を祈れ」との言葉を託されました。
この場面には、人から人へと「教えの灯」をつなぐ厳粛さが感じられます。
最澄との交流と学問の深化
帰国後、空海は比叡山の最澄と交流します。
最澄が空海のもとで灌頂を受けようと決意したのは、空海が持ち帰った経典・曼荼羅・法具の体系的な充実に驚いたからでした。
その姿勢には、自分の不備を認め、他者から学ぼうとする謙虚さが感じられます。
教育と社会へのまなざし
晩年、空海は高野山に拠点を移し、教育にも力を注ぎました。
特権階級だけが学べる時代に、「教育の機会均等」を唱えたことは驚くべきことです。
その思想は、まさに現代にも通じる普遍的な価値観といえるでしょう。
永遠の禅定へ
835年3月21日、空海は予告通り、瞑想したままの姿で入定しました。
以来、「お大師様」として親しまれ、宗派を超えて尊敬され続けています。
江戸川柳の「大師は弘法にとられ」という言葉に象徴されるように、今も日本人の心の中に生きている存在です。
余話 ― 密教とその後
戦国時代、高野山は織田信長や豊臣秀吉の攻撃を受け、多難な時代を迎えます。
それでも密教は、曼荼羅や印契、儀礼などの象徴的な方法で深い教えを伝え続けました。
目に見えない真理を「形」で表すこの発想に、芸術的な魅力を感じます。
終わりに
「空海と真言宗」は、宗教書でありながらも人間・空海の生き方を感じさせる一冊でした。
常に自らの信念を貫き、権力に寄らず、知を極め、人々の幸福を祈り続けたその姿勢。
千年以上経った今も、私たちに多くの示唆を与えてくれます。
備忘します。
>
空海は大学へ入ったものの、1年余りのうちに中退してしまった。1族の人たちはたいそうがっかりしたことだろう。1族の期待を一心に受けて、大学まで進学、儒教を中心に学び、将来は律令国家の官吏として立っていく気がまえで望んだ道であったが、それだけでは満たされない何かがあったのかもしれない。ページ24
室戸岬では空海は、過酷な自然の中で修行を続けていた。空海修行の霊跡が御厨人洞窟だ。ある日突然、明星が近づいてくるのが見え、口の中に飛び込んできたのだという。ページ27
東大寺の要職に就く何人かが、空海の才能を見抜いており、また華厳経を学ぶものにとっても「華厳経」の思想を重視する空海の入唐はマイナスにはならないと思ったのであろう。東大寺を中心にする南都六宗の有力者が、空海の留学の実現に向けて、力を貸してくれたに違いない。ページ38
空海が永遠の師となる恵果と運命的な出会いをしたのは、6月上旬のことだった。恵果は不空の直径の弟子で、長安で純密の正系を伝えるのは恵果ただ1人だった。ページ44
恵果は周りの雑音などに惑わされはしない。密教の最高の位である阿闍梨の即位の式典である。8月上旬、恵果の手によって取り行わた。密教の7祖が恵果、ここに8祖の空海が誕生するのである。ページ48
空海の入唐の目的は正純密教の本質を極めることであった。幸いにも恵果に出会い、短期のうちに密教を学ぶことができた。恵果は「かくなる上は一刻も早く日本へ帰ることだ。そして密教を広め、万民の平安を祈れ」と空海に言い残していたという。ページ50
嵯峨天皇、空海、橘逸勢の3人を書道の名筆、当代の三筆と言う。橘逸勢は、空海と同じ船で入唐した留学生で、その後も長い交際が続いた。ページ58
最澄が空海から灌頂を受けようと決めたわけは、空海が唐から持ち帰った正純密教の経典類。曼荼羅、法具が、体系的に数多く集められていたことに驚いたからだった。自分の不備を知り、空海に教えを乞うしかないことをすぐに悟ったであろうと考えられる。ページ62
密教はその頃、朝廷や国が注目し、求めているものだった。自分の密教の不備を知った最澄は、空海の灌頂を受ける決心をしたのである。当時の灌頂の仏教世界における地位を考えると、まさに異例のことだった。ページ63
空海が高野山に住むようになったのは832年時に59歳であった。ページ71
当時の社会情勢を考えると、特権階級だけの教育の機会に対抗するもので、無益であるとか、成果が期待できないという意見も多かった。空間の教育の機会均等という考えは、現代社会の通じる考え方である。ページ81
835年3月21日、朝がまだ開けない頃に、空海は予告通りに瞑想した姿のまま永久の禅定に入った。ページ84
「大師は弘法にとられ」という江戸川柳がある。単に大師という場合には、弘法大師、空海を指すほど身近な存在だという意味だ。このように「お大師様」と親しまれ、宗派を超えて日本の人々に尊敬され続けているのが真言宗の祖、空海なのである。ページ85
戦国時代以降は、高野山も根来寺も多難な時代を迎える。天下統一を目指す戦国大名の織田信長と豊臣秀吉から、攻撃を受けるという試練が待ち受けていたのである。ページ102
微妙で奥の深い教えは言葉や文字で伝えるのが難しいからである。そこで密教では、曼荼羅や印契、陀羅尼、儀礼などの様々な手法を使って教えを示してきた。ページ130
「末期の水」お別れの儀式の始まりで死水という。亡くなった直後に、最後の別れとして口元に水を捧げる。これは仏陀が入滅直前に水を求めたという言い伝えによる。ページ178
弔辞は、個人の威徳を讃えながら述べられ、故人の少史、業績、思いなどを語る。弔電を打つ人は、自分の言葉でお悔やみを述べたい。ページ195
お墓参りをする時は、最初に掃除をする。手おけと柄杓は、菩提寺・霊園に自家のものを用意しておく。お席の周囲を掃き清め、雑草を取り植木の剪定をする。墓石はスポンジで洗い乾いた布で拭き、文字は歯ブラシなどできれいにする。外側も水洗いする。花立てをきれいにして、持ってきた花を供える。お供えは、半紙を乗せてろうそくを灯しして線香を上げる。火をつけるのも忘れないこと。墓石に功徳水をかけて、合掌礼拝する。お参りが済んだら、犬・猫・からすなどが荒らすことがあるので、供え物は持ち帰るようにする。ページ214
<<