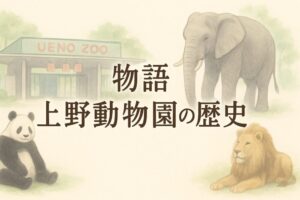熊谷公夫さん(東北学院大学文学部教授)の著した『大王から天皇へ』を読みました。
論文形式の歴史書は難解な表現が多いのですが、本書は非常にわかりやすい日本語で書かれており、学説が分かれるテーマに対しても著者が自らの立場を明確に提示していて、たいへん好感が持てる一冊でした。
「天皇」という称号の成立
本書の大きなポイントは、「天皇」という呼称がいつ、どのように成立したのかという問題です。
従来、推古朝説もありましたが、近年は天武天皇期に成立したとする見解が有力とされています。
「治天下大王」から「現神御宇天皇」へ
「王の中の王」である大王が、天武天皇の時代に「神格を帯びた天皇」へと飛躍したことを筆者は強調しています。壬申の乱を勝ち抜いた天武天皇が、現神として人々に認識され、以後「天皇」という存在が確立されたというのです。
まさに「天皇」も「日本」も、内乱とカリスマ的指導者の登場という特殊な歴史状況の産物だった、と理解できました。
日本と東アジア世界のつながり
読んでいて特に印象的だったのは、日本列島が古代から中国や朝鮮半島と深く結びついていたという点です。
鉄の独占と支配力
4世紀以降、倭王権は半島ルートを掌握し、鉄や先進技術を独占・再配分することで支配力を強化しました(p.30)。
倭と半島諸国の関係
倭国は百済や加那諸国と同盟関係を結び、対等な外交を展開していたことがわかります(p.45)。
冊封体制からの離脱
邪馬台国の卑弥呼や「倭の五王」以外、基本的に冊封は受けず、独自の王権を歩んだことも確認されます(p.83)。
外交と国内政治の両面で、列島が東アジアの情勢に強く影響を受けていたことを改めて理解しました。
渡来人と仏教の受容
本書では渡来人の存在がたびたび強調されます。
仏教受容の初期にも渡来系の人々が深く関わり、外来の宗教を受け入れる素地を持っていたことが印象的でした(p.204)。
感想
歴史書を読むと「天皇」という存在が太古から神格化されていたかのような印象を受けがちですが、本書はそうではなく、天武天皇のカリスマ性と歴史的状況が「天皇」号成立の決定的要因だったことを明快に示してくれます。
また、倭王権が半島との交流を通じて鉄や文化を取り入れながら発展していった姿も鮮やかに描かれており、日本史を東アジアの中で捉える重要性を再認識しました。
非常に読みやすく、それでいて学術的にも深みのある本でした。
備忘します。
>
天皇の成立時期については推古朝説もあるが、最近は天武朝説が有力視されている。ページ9
「治天下大王」から「現神御宇天皇」という称号の変化の背後には、列島の君主の「王中の王」から「神」への飛躍があった、というのが筆者の考えである。ページ13
このようにカラ=金韓国は、倭人にとって、古くからの半島の窓口であり、最も身近な外国であると同時に、先進文物を供与してくれる、かけがえのない大切な国であった。ページ23
ルートを掌握した倭王権が倭人を集団で半島を送り出した目的は何であったのか。列島と半島の交流で、近年特にその重要性が指摘されているものに鉄の問題がある。ページ29
このように、4世紀前半のヤマトとカラの出会いは、倭王権による半島ルートの掌握を意味した。それによって倭王権は、鉄を始めとする必需物質や先進技術・威信財を独占し、その再配分という公共機能を持つことによって各地の首長に対する支配力を強めていったのである。ページ30
公開土王碑の再検討の結果、一時的にではあるが、倭 は百済、新羅両国を臣民とした、というのが、文脈に即した辛卯年条の大意であることが確か見られた。しかし碑文は公開土王碑の武勲を強調することに主眼が置かれており、そのため一定の誇張が含まれている。ページ43
公開土王碑にみえる倭が、列島を公的に代表する王権である事は、もはや確実といって良いであろう。ページ44
4世紀後半には、倭国が以前からの友好国である加那諸国に加え、百済とも同盟関係を結んだ。倭国とこれらの半島諸国との関係は、客観的には、支配隷属関係では決してなく、基本的に対等の関係であった。しかし、加那諸国は小国であったから、倭国との間にある程度の依存と保護の関係が形成されてくる事は否定できないであろう。ページ45
戦乱はカラの人々に移住を決意させた直接の要因となったろうが、より根本的には大和とからの間に歴史的に形成されていた太いパイプが彼らを列島に導いたと見るべきであろう。個人が集団で居住していたカラの人々にとって、大和は身近な存在になっていた。ページ60
こうしては、冊封体制から離脱する決意をして中国王朝と決別し、独自の天下的世界の王としての道を歩み始めたことになる。その理由は、何といっても、列島の支配者としても地位の維持に、もはや中国王朝の権威を必要としなくなった、ということであろう。ページ82
…東アジア世界の外交形式として作法を重視しているが、実は、古代の列島の君主が中国の皇帝に冊封されたのは、邪馬台国の女王卑弥呼と和の五王だけであった。ページ83
河内の勢力が古市、百舌古墳群の巨大古墳を造営したと見るのはやはり無理で、大和の勢力が何らかの理由で河内に王墓を作ったと考えるしかないと思われる。ページ94
やはり「天皇」号成立以前の列島支配者の正式な君主号としては、現時点では「治天下大王」を置いて他に考えがたい、というのが筆者の結論である。ページ123
この5世紀後半の半島の戦乱は、列島の歴史にも多大の影響を及ぼした。ページ128
こうしてワカタケル大王の時代は、冊封体制からの離脱、「治天下大王」の成立、渡来人の第2波、旧豪族の没落などが相次いで起こり、列島社会の歴史はさらに次の段階に足を踏み入れていくのである。ページ131
…内乱説には現時点では賛同できないが、継体、欽明朝の政争を王権内部の大位継承争い、ないし派閥交渉という次元に限定するのであれば、確かにあったと思う。ページ143
大伴氏を安閑。宣化の擁立者、蘇我氏を欽明の支持者と考え、その背後に大伴、蘇我両氏の政治的対立を想定したが、この点に関してはその通りであると思う。それを裏付けると思われるのが、大友金村が失脚する事件だ。ページ144
要するに未満な日本府とは未満な復興と言う王権の当面する外交目標を実現するために、金明町書面に安羅に置かれた軍事外交権を持つ出先機関であった。未だ日本府の存在は、それ以上でも以下でもなかったというのが筆者の考えである。ページ164
6世紀の倭王権は機構による支配に大きく踏み出したが、支配機構の内部構造は、多分に人格的結合に依存した氏ごとの縦割り支配であって、多元的な君主関係が広範に存在していた。大王のもとに君主関係が一元化されていないということが、やがて様々な弊害を生み出していき、それが大化の改新の重要な原因の1つとなっているのである。ページ189
馬子とともに早期の仏教に関わった人々が、ほとんどが渡来系の人々であった。半島からやってきた渡来人は、もともと外来の宗教である仏教を受け入れやすい素性を持っていたのである。ページ204
結局、唐側も倭王権の外交方針を受け入れ、その後、冊封を受けないことが対中外交の基本方針となる。推古朝の対隋外交は、新しい対中外交の出発点になり、大陸ルートを最新の中国文化の受容ルートとして切り開いた点で高く評価できよう。ページ230
推古没後の王位継承をめぐって、調停はもめにもめた。この時点での有力候補は田村皇子と山城大兄皇であった。ページ242
蝦夷が強硬手段に訴えて摩理勢を除いたことで、ようやく田村皇子即位が実現する。舒明天皇である。ページ244
蘇我入鹿の専横ぶりに憤慨していた鎌足は、王族に君主と仰ぐにふさわしい人物を探し求め、中大兄皇子に目をつけた。中大兄皇子は、舒明・皇極両天皇の間に生まれた王子で、次期大王の候補として血筋的には申し分なかったが、兄に蘇我氏が後ろ建てとなっている古人大兄皇子がおり、このままでは王位が巡ってくる可能性がまずない。ページ252
先に推古死後の王位継承において、推古の意思が重きをなしたことを見た。大王の意思を尊重するという傾向は、既に群臣層に胚胎していたのである。このような素地があったところに宮中のクーデターと言う突発的事件が起こり、譲位という新たな王位継承方式が実現することとなった。ページ256
このような支配イデオロギーを、臣下に宣伝し、浸透させる場が朝庭であった。改新政権は、朝賀などの国家的な儀式や重要な法令の発布のたびに、臣下たちを呼び集めて朝庭に整列させ、天つ神の「事依させ」を受けた大王だけが天下を統治できる正統性を持っていることを宣り聞かせて、大王の隔絶した権威を繰り返し感得させた。ページ275
655年正月、宝皇女はかつて政治を取った飛鳥板蓋宮で即位する。史上初の重祚である。皇極天皇と区別して斉明天皇という。ページ279
しかしそれにしても、中央政府の派遣した遠征隊、征討軍が北海道まで行ったのは、古代ではこれが唯一である。斉明朝は北方政策でも、全く前後と隔絶しているのである。ページ306
このように見てくると、重祚した女帝生命の二大「興事」である石の王都、倭京の建設と北方遠征は、須弥山像を中心とした飛鳥寺西の儀礼空間を媒介に結びつくことがわかっていただけたのではないかと思う。ページ297
…大海人方が軍事的に優位に立つと、諸国の国宰や大和の豪族などが流れを打ってを大海人方につき、近江方の将官からも寝返るものが出た。この現象には、軍事的状況に加えて大王弟、大海人にもともとそなわっていた高い権威が大きく作用したと思われる。ページ332
天武天皇はまさしく律令国家の建設を先頭に立って推進するカリスマ的政治指導者といって良い。神は神でも、信仰の対象としての神というよりは、自ら実施する新たな政策をその神的権威によって正当化するという政治的な神なのである。ページ335
持統天皇の時代には、ただ天皇といえば天武天皇の事だという認識があったことになる。ページ336
要するに、「天皇」という二文字に込められた理念は、天つ神の系譜を引く神で、皇帝に準じ格を持った君主ということになる。基本的には固有の神話観念に裏打ちされた称号であって、ここに道教の影響を明確な形で見出す事は困難である。ページ340
…列島の君主は決して太古の昔から神であったのではないということである。壬申の乱に勝利し、人々から「大王は神にしせば」とあがめられた強烈な神的権威を持ち主であった天武こそが、現神「天皇」と「日本」の生みの親であった。天皇も日本も未曾有の内乱にカリスマの出現という、列島社会が高揚した特殊な歴史状況の産物だったといっても良い。ページ347
人間宣言によって神としての天皇の歴史出を打つことになったのも、敗戦という歴史的状況であった。神としての天皇は、もはやその歴史を終えたのであり、同時に天皇の統治する神の国も永久に日本の歴史から姿を消したのである。ページ347
<<