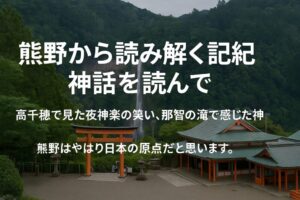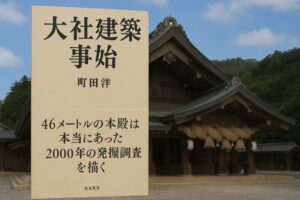古本屋で偶然見つけた一冊。西成彦先生(東大卒・熊本大学)の著書『フカディオ・ハーンの耳』を読みました。
ちょうど調べていた矢先、来年10月から朝の連続テレビ小説「ばけばけ」が、ハーンの妻・せつさんをモデルにした物語だと知り、まさにセレンディピティに驚かされました。
ハーンへの批判と評価の間で
本書は、ハーンを絶賛する伝記とは違い、かなり批判的な視点が込められています。
確かに著者の言うことにも一理ありますが、当時の時代背景を考えれば「求めすぎ」では?と思う部分も多々ありました。
ハーンが日本を理想化しながらも、迷いや葛藤に揺れていたことは事実でしょう。
しかし、彼が残した作品が今なお読み継がれ、日本文化を世界に伝えた功績は大きいとあらためて感じます。
印象に残ったポイント
「耳なし芳一」の創作背景
松江で大黒舞に触れ、非文字文化と芸能に深く関心を寄せたことが、傑作誕生の源泉だった。
「夏の日の夢」(熊本時代の成果)
浦島太郎に自身を投影し、43年間の人生を重層的に描いたエッセイ。旅行記にして自伝的。
本妙寺のハンセン病患者との遭遇
彼の反応は「判断停止」に近かったが、キリスト教宣教師の横暴に対する批判は明確。
「耳なし芳一」の結末解釈
和尚の独占欲と芳一の純情、そのねじれた関係を描きながら、最後は耳を失わせることでユーモアすら漂わせる。
「魔性の女」の系譜
「雪女」「おしどり」と同じく、宿命的な女性像を描いた一連の作品群に連なる。
感想
ハーンの業績には「到達できた部分」と「できなかった部分」が確かにあります。
しかし、彼の日本理解を「西洋的限界」と切り捨ててしまうのはもったいない。
異文化の翻訳者として、日本を世界に紹介した功績は揺るぎません。
『耳なし芳一』に込められた想像力、日本の民衆への眼差しは、いま読んでも強い力を持っています。
このタイミングで本書と出会えたことは、自分にとっても偶然以上の意味を持ちました。
来年の朝ドラ「ばけばけ」を楽しみにしながら、もう少しハーンの世界に触れてみたいと思います。
👉 次は『怪談』を久々に読み直してみようかなと思っています。
ラフカディオハーン #ばけばけ
✍️ 備忘引用
>
彼は市内を徘徊しながら耳をすませているだけではなかなか耳にできそうにない、とびきり秘境的な音楽に触れるべく潜入調査に踏み切った。…人通りの少ない山道を友人と2人でたどり着き、大黒舞に触れることのできた感動を高ぶりとともに書き残している。ページ29
「耳なし芳一」こそは、ハーンのこの一連の関心の中から生まれた最初で最終の傑作だったのである。ページ40
1893年の夏…熊本時代最初の成果である「夏の日の夢」を一気に書き上げた。旅行記の体裁を踏まえながら、浦島太郎に自身を投影させ、イオニア海の小島に生まれてから、熊本に来るまでの43年間を振り返ったこのエッセイは、その主題と素材の重層性において、極めて注目に値する作品である。ページ46
ハーンが見た松江の大黒舞の形式は、この芸術進化論の立場からすれば、この第二段階の形式を典型的に表したものだと考えることができる。要するに、ここは語りと囃の分業について語っているのである。ページ55
…古事記と大黒舞とは、それぞれ太古の非文字文化を継承した日本文芸の一部である点では共通する。…万世一系の天皇制を支える国家創設神話としてバイブル並みの扱いを受けるに至った古事記…一方、大黒舞は、祝福芸として古代から近世に至るまでもっぱら口碑に受け継がれ、偶然のように書き留められることがなかったわけではないにせよ、時代の権力者に媚びへつらい、中世近世以降は希代の逆賊平将門の末裔とささやかれた非差別職能集団の間に伝わっていった伝統芸能の一つである。ページ59
本妙寺に集まるハンセン病患者の群れに対するハーンの観察と反応は、判断の停止に近かった。ページ81
狐憑きの解消に、キリスト教は何一つ貢献しなかったと言い切ることで、ハーンは、キリスト教宣教師の横暴に一矢を報い、教育を通した迷信の打破という近代化により実効性を認めた。ページ84
本妙寺のハンセン病患者は、キリスト教団の慈善事業や、明治40年以降に日本政府が開始した隔離医療の方策を尻目に、一向にその数を減らそうとはせず、1940年、熊本県警が国立九州療養所との合作で、検束の名の元に行った一斉検挙の後、初めて街頭から消滅する。ページ87
ハーンは滅亡冬には弱く、松江でも真冬に風邪をこじらせ寝込んでいるところにせつが身の回りの世話役としてやってきたことが、2人の馴れ初めであった。ページ107
ヨーロッパの中世が、ハーメルンの笛吹きと、その音楽に引きずられ、憑かれたように隊列を作って行進し始めてしまう群衆と、その有り様をただ望然と眺めているしかない無力な庶民たちからなっていたとすれば、同じことが中世の日本についても指摘できるはずである。ページ148
日本の民衆は、ハーメルンの笛吹を単なる詐欺師だの悪党だとみなしたりせず、必ずいたわるはずだと希望的に考えることで、彼自身もまた疎外感から癒える。それがハーンの日本における14年間だった。ページ151
…ハーンは笛吹きにも、また騙されやすい音楽好きの子供にも、またそういった迂闊な子供の将来を案ずる親にも自らをなぞらえうる想像力によって、日本版妖精文学の傑作「耳なし芳一」を書き上げることができた。ページ157
そんな芳一を民衆の手から、ひいては平家の亡霊たちの手からもぎ取って独り占めしたのは、阿弥陀寺の和尚の方であった。…問題の惨劇は、阿弥陀寺の和尚の独占欲と、生活の安定という餌に釣られた芳一の純情さに端を発していた。ページ168
耳なし芳一の話は、最終的には阿弥陀寺の和尚の勝利によって、三角関係に決着がついたかのような終わり方を見せているが、必ずしもそうとは言い切れない面を残している。ページ180芳一に富と名声を保障しながらも、同時に、彼に耳なしのStigmaを負わせることによって、この生のいずれにも軍配を上げずに済ませてしまったハーンのユーモアは、ここにも生きているといえる。ページ183
「魔性の女」-「おしどり」といい「雪女」といい、ハーンの作品の多くは宿命的な女性を描くことに捧げられている。「耳なし芳一」もまた、そういった作品の系譜につながるものだとはいえないだろうか。ページ186
<<