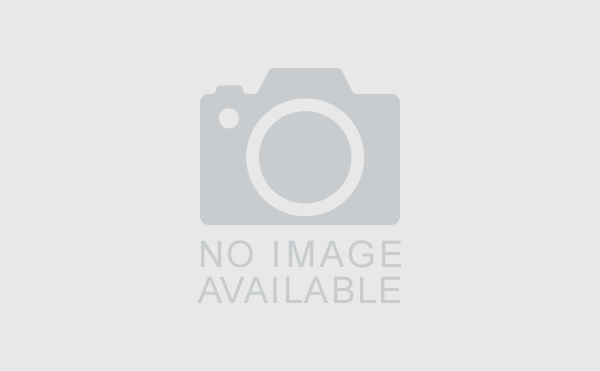「神々のさすらい」を読みました。播磨風土記を解説した本です。学芸大学の古本屋で見つけました。風土記について書かれた本は初めて読みました。元明天皇の勅命で編纂された風土記で現存しているものは5つであることを知りました。そのひとつ播磨風土記を古事記、日本書紀との関連で読み解いています。アメノヒボコ、神功皇后、応神天皇、仁徳天皇、オケとヲケがでてきます。著者によれば大和朝廷に気を遣いながらも伝承をまっすぐに伝えているとの評です。尚、この本はノンフィクション賞の出品作品で、受賞は逃したものの、小松左京さんが出版の橋渡しをしたとのことです。備忘します。

神々のさすらい―「播磨国風土記」の世界 (1979年) (角川選書〈105〉)
- 作者:寺河 俊人
- メディア: -
もともと風土記は、各国の地名のいわれ、産物、土地柄の良否等を報告させようとして、和銅6年(713年)に元明天皇がその作成を命じたものである。いち早く提出された播磨国風土記は命令に愚直なまでに忠実に、地名由来としての神話を述べている。したがって、神話が細切れの恨みはあるが、他にどんな意図もないだけに、かえって神話そのものが伸びやかに息づいている。これが播磨国風土記の大きな特徴であり、私が風土記の世界へ引きずられていった第一の理由もほかならぬその1点にあった。ページ11
現在古風土記として残っているのは、出雲、播磨、常陸、豊後、備前の五国にすぎない。その中で播磨風土記は、和銅6年(713年)の風土記編纂の勅命をわずか2 、3年でまとめあげられたものとされている。ページ16
この古写本が研究の対象となったのは、江戸時代の後期、それまで長く三条西家の文庫の中に秘蔵されていたものを、ある好事家が転写したのがきっかけであった。これでようやくその存在が知られたのであったが、それでもまたまだごく一部の間に限られていた。古写本の三条西家本そのものが、復刻版として世に出されたのは大正15年のことである。長い眠りに比べれば播磨国風土記は今めざめたばかりだともいえる。ページ17
ところが一方の伊和大神は、天日槍の命の思いがどうであれ、ひたすら勝利に酔う。無理もない。出雲族と共に播磨入りして以来、土着の神と部族との戦いに苦しみ、内訌を抑えてようやく播磨平定を終えようとする矢先に、待ったをかけたのが天日槍の命であったのだ。…先進文化で武装した天日槍の命軍は強力であり、だからこそ、強敵の紙を但馬に立ち去られせた事は、兎も角も、大勝利であったのだ。ページ143
神功皇后の伝承の一本の柱は神神への祈りである。海路の危険に加え、戦う相手の強い勢力を思うにつけても、人を超えた力への祈りが欠かせなかったのは当然のことであり、その真剣さが行間ににじみ出ている。東から追っていくと、伝承はまず、明石市魚住町の住吉神社近くの海辺から始まる。海上を漕ぎ渡ってきた神功皇后に対して、住吉大社の分身と思わせる神が赤土を差し出していう。「新羅の国を、丹浪もちて平伏け賜ひなむ」ページ205
祭祀と狩り。ここまで応神天皇の足取りを追ってきた、次に取り上げなければならないのは大和朝廷の権力を背景にした天皇の強大な振る舞いである。これらの記事を読み進んでいくことで、いかに大和朝廷が安定した勢力を誇り、桑の葉を蚕食するように中央権力が播磨国に侵入していったかが納得させられる。ページ225
この残虐な事件の結末が播磨国風土記の世界に引き継がれるのである。つまり、無残な殺され方を市の辺の忍歯の王の2人の皇子、オケとヲケは危害が自分たちを及んでくるのを恐れて播磨に逃げてくる。無理もない。大長谷の王子は後に雄略天皇となるのであり、この天皇が横暴であった事は史書が共通して指摘することだ。二皇子の逃避行が始まる。ページ238