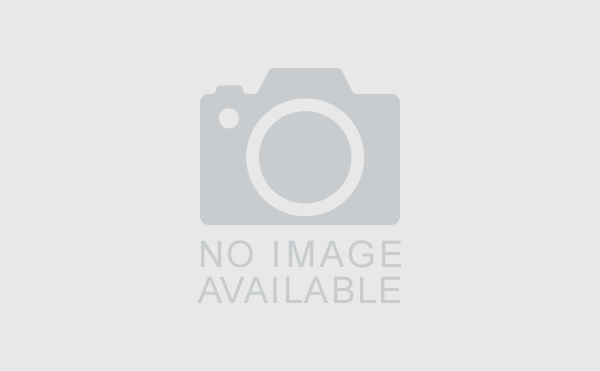「ファンダメンタルズテクニカルマーケティング」を読みました。仕事のための読書です。ウェブマーケティングの概略を解説した教科書のような本です。4ヶ月ほど前に一読しました、再読です。youtubeや専門家からのレクチャーを聴いていることもあり、再読で自分の成長がわかりました。
この本を読めば、すぐ実践できて、成果が出るわけではありませんが、外部依頼やチームでの議論をする際に、最低知らなければならない基礎知識です。備忘します。
具体的なテクニックについては、まだまだですが、全体像がおぼろげにわかってきました。ウェブにおいても、製品の本質(特徴、価値)が起点で、必要な人に伝えて、購入してもらうという普通の商売です。伝える方法がウェブに変わっただけですが、ウェブの理解がないと「売れない」と断言しています。
マーケティングは30年前も今も「誰に」「何を」「どう伝えるのか」が重要なのだ。ウェブマーケティングは、この「どう伝えるのか」の部分がウェブに置き換わっただけであり、「誰に」「何を」の部分は30年前から一切変わっていないのである。ページ310
ウェブにおいてはこの商品を欲しいと言う人を探すことが簡単にできる。つまりコミュニケーションコストが劇的に下がったのである。ページ26
ターゲットユーザを複数指定して、そのターゲットユーザごとにその商品の何を伝えるかを考える必要があるのだ。ページ39
ここからわかるように、ターゲットはその商品特徴に興味を持つ人に設定しなければならない。…コンセプトワークがきっちりしており、誰に何をが明確に決まっていれば、ストレートな表現でもユーザの心にきっちり刺さる。ページ42
「誰に」「何を」決めるにはまず、その商品全体、ユーザ、競合情報の3つを知ることから始まる。ページ48
…何度も消費者に話して反応見ながら、この商品の売りの部分を探していく必要がある。これはアンケートなどではなく、必ず対面でやるべきである。「なぜ響かないのか?なぜ興味を持ったのか?どう言い換えたら興味を持つのか?」などをその場でキャッチボールしながら確かめることが必要だからだ。ページ55
このことからわかるように、マーケットは自分でインタビューできるようにならなければならない。いつまでも他人から与えられてもらった情報でクリエイティブを作っている限りは、アシスタントやオペレーターの域を超えられず、本物のウェブマーケターにはなれない。ページ57
ここで、検索キーワードについては、キーワードアドバイスツールなので機械的に抽出するだけで終わってはいけない。…このキーワードは商品起点のキーワードでしかない。ユーザ起点でキーワードを考えることの方がもっと重要だ。このようによこのように、あくまでも商品起点だけではなく、ユーザ起点でも競合を知ることが大事だ。ページ63
この競合はどうすれば炙りだすことができるだろうか?私が行っているのは4段階セールスコピーと言う方法である。ポイントは、競合を選択肢と考えることだ。次のように進めていく。まずターゲットユーザを想定した場合、4段階のドリルダウンで選択肢をつぶしていく。「誰に」が決まった後はターゲットにこの商品の「何を伝えるか」を考えるこ。れは広告のメインメッセージと考えると良い。ベジ90
USPとはユニークセリングプロポジションの略で商品やサービスが持っている独自の強みのことである。このUSPは主に大きく4種類に分けられる。①他社商品にはない便益を与えられるか今までになかった便益を与えられる ②他者商品よりも高い便益を与えられる ③実績、異性などの付加価値がある ④金銭的金銭金銭的お得感がある。ページ91
USPとは世の中で家の商品でしか提供できない価値のことだ。ページ94
人との関係を男性は「勝ち負け」、女性は「共感」で考えることが多い。ページ99
…中でも特に、セールスレターなどのボディーコピーを書く際には構成が重要である。一つ一つの文章がしっかりしていても、文章の並べ方がおかしければ、伝わるものも伝わらない。…この処方ではまず文章を5つのブロックに分ける。①結論 ②否定 ③肯定 ④自分の意見 ⑤煽りコピーは最後まで読んでもらえる前提で書いてはならない。最初の1、2行でユーザの心をつかめないと、その後どんな良いことを書いても読まれる事は無い。だから絶対に伝えたい事は最初に伝える。ページ118
エモーションリレーを見直すことで、成果が激増したケースが何度もある。だから、文字通り感情のリレーがつながっているかなので実際に人間が広告をクリックして読み進めて判断することが大事だ。ページ122
そして、大切な事は多くの人はキャッチコピーやボディーコピーにはこだわるが、マイクロコピーにこだわる人は少ないということである。だから、マイクロコピーの力で売り上げが2、3倍になっても、他社にはなぜ2、3倍の売り上げになったのか理解できないので真似されず…ページ127
つまり、データからいかに人間感情を読み取れるかが、ファンダメンタルズ運用においてはとても大事な工程になる。ページ138
しかし「誰に」が旧メディアより精度が上がったところで、クリエイティブをおろそかにすると、「何を」の機能が下がり、結局効果を相殺されてしまってウェブマーケティングは旧メディアマーケティングより劣化する。ページ141
この商品のマーケットはどんなマーケットか? マーケットの中でこの商品の特徴は何か? このマーケットのユーザはどんなユーザなのか? これらを考え、誰に何をどうどのように伝えるかに頭を使う。そしてそれをウェブのテクノロジーに落とし込む。ページ142
クリエイティブにおける暗黙知はファンドメンタルズクリエイティブから生まれ、形式知はテクニカルクリエイティブから生まれる。ページ155
結局文章が多くて長いLPが読まれないのではなく、面白くない文章を読まないという当たり前のことだった。私の経験上、最後まで見られるLPは文字が少なく短いLPが多い。しかし売れるLPは文字が多く長いLPが多い。言い換えると文字が多く長いLPは最後まで見られることが少ない。ただし、文字が多く長いLPは最後まで見られると購入される率は高い。ページ160
何を言うかを決めるという事はその商品のコンセプトを決めるのと同義だ。まず最初に商品、ユーザ、競合のことを徹底的に調べ上げて100個のネタを洗い出すことが大事だ。ページ164
ABテストは練りに練ったクリエイティブの中で、どれが最も優れているかを見るものである。ABテストは最高のクリエイティブが2個以上作れる人のみに許された方法であることを覚えておいて欲しい。ページ166
①先にクリエイティブを見る ②仮説を立てる ③データで仮説の答え合わせをする ④仮説には出てこなかった課題データから見つける。ページ180
SEOに関して言うと、私の観点ではあまり重要ではないと考えている。ページ182
社内リソースが足りない場合は広告代理店に依頼せざるを得ないと思うが、利益相反関係であることを理解した上で依頼する必要がある。ページ206
ウェブマーケティングは、売り上げを最大化すれば、後追いで利益が最大化されるわけではない。ページ206
最適獲得単価で獲得できる「上限件数×最適獲得単価」が最適広告費である。それ以上なら過剰投資だし、それ以下なら機会ロスとなる。ページ207
大体の場合、広告を自社や自分のお金で運用している人は時間単位でチューニングしている。ななぜなら広告費が赤字になると、すぐにストップしなければならないからだ。ページ213
データから人間の行動パターンを見つけ、そのパターンの背景を理解し、販促につなげることが本当のマーケティングだ。ページ216
まずウェブ広告においては、「広告主、メディア、ユーザ」の3つの視点を十分に把握しておく必要がある。相手の立場がわからなければ、商売で利益を出すことはできないからに他ならない。ページ221
様々な切り口の広告を作成しようとしたときに問題となるのが、広告と飛び先販売ページの整合性だ。ページ237
このことからもわかるように、息の長いメディアは必ずユーザ>広告主である。立ち上がり機のベンチャーメディアは、最初は目先の売り上げのためにユーザ<広告主となってしまうが、ある段階からこれを入れ替えないと、だんだんとユーザ離れが起きる。ベジ248
その一行の思いを感じ取る通販は、たった一行で事業がうまくいったり失敗したり、運命を左右する可能性があることを知って欲しい。たかが一行されど、一行、魂を込めた一行を綴るマーケッターになってほしい。ページ260
1000円を1300円にするとさえわかっていれば良いのだ。細かい数字こそが1番大事な数字だ。そして小さく生んで大きく育てるのだ。億単位の話をする前にはまずは、1000円を1300円にするシュミレーションをしよう。ページ271
マーケターが自分でシステムがいじれるのと、いじれないとでは、生み出せる価値は100倍位の差が出る。ページ277
ブランドは信頼という一朝一夕では作られない要素で消費者の購買決定の判断に大きな影響与えているが、なかなかそれが機能しづらくなってきている現状がある。というのは、商品群としてのブランドの優位性よりも、商品単体、つまりプロダクトの優位性が高くなっているからに他ならない。ページ278
だからEコマース企業はフルラインナップ戦略ではなく、完全にアフターフォロー責任を終える範囲に絞って商品を発売すべきなのだ。ページ286
まずは自力で目の前の1人のお客様を満足させて濃いファンにしていき、それを地道に1000回繰り返して1000人のファンを作る。そこまでいくとお客様をファンにする方法がわかる。ページ295
誰かがファンを連れてきてくれるのではなく、自分で直接ファンを作ることが大事だ。そのためにはまずは目の前の1人のお客様を満足させることだ。ページ296
マーケティングは30年前も今も「誰に」「何を」「どう伝えるのか」が重要なのだ。ウェブマーケティングは、この「どの」の部分がウェブに置き換わっただけであり、「誰」「何」の部分は30年前から一切変わっていないのである。ページ310