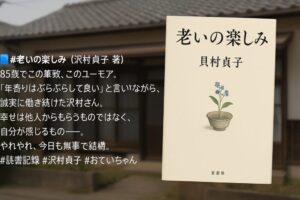明治という時代をフランス人の目を通して見直す本
「ビゴーが見た日本人」を読みました。
もともと私が多くの本を読む理由は、突き詰めれば「自分はどこから来たのか」「自分とは何か」を知りたいという思いからです。その中で避けて通れないのが「日本人とは何か」という問いでした。
私は昭和29年生まれ。戦後教育を受けて育ちましたが、その根の部分には、明治・大正・昭和前期という「前の日本」が深く流れているのを感じます。子どもの頃、品川の下町で体験した風景や人の気配――それはまさに古い日本がまだ息づいていた時代でした。街が整備され、トイレがきれいになり、治安が良くなっても、私の中の原風景はあの頃の日本にあります。
この本を読んで、「ああ、そういうことだったのか」と腑に落ちました。明治という新しい時代が、人々の生き方や価値観をどのように変えていったのか。ビゴーという一人のフランス人画家が、その変化を絵に刻んでくれていたのです。
明治を描いたフランス人画家
ジョルジュ・ビゴーは1860年、パリに生まれ、明治15年に日本に渡りました。母は画家で、彼自身も幼い頃から絵に才能を示したといいます。横浜に到着したのは47日間の船旅の末のこと。以後17年間、日本で暮らし、新聞の風刺画やスケッチを通して、明治の人々の姿を生き生きと描き出しました。
ビゴーは日本女性と愛し合い、子をもうけ、そして帰国する際にはその子を連れてフランスへ戻ります。彼の人生は、まさに日本の近代化とともにあったのです。
近代化の光と影
本書の中で特に印象に残ったのは、彼の描いた「近代化の影」の部分でした。
「近代化は日本の社会の支柱を精神主義から物質主義へと駆り立てていた。人口の増大、欲望の増大などによって、すべて金を中心に考える世の中へと変身しつつあった。」
――ページ55より。
明治の急速な西洋化の裏で、価値観が揺らいでいく日本人の姿に、彼は深い寂しさを覚えたのでしょう。
また、銭湯や混浴、風呂敷、遊郭といった庶民の生活にも目を向け、驚きとユーモアをもって描き出しています。たとえば「出っ歯の魚屋」や「風呂場のスケッチ」など、外国人ならではの観察眼が光ります。風刺でありながら、どこか愛情も感じられるのが不思議です。
日本の「素顔」を描いた鏡
私がこの本を通して感じたのは、「ビゴーの絵は鏡だ」ということです。
彼が見た日本人の姿――それは、急速に変わろうとする日本の明暗を写し取った鏡であり、私たち自身の心の奥にある「古い日本人らしさ」を思い出させる鏡でもあります。
現代の私たちは、清潔で便利な社会に暮らしながらも、どこかで「何か大切なものを失っているのでは」と感じることがあります。その感覚の原点を、ビゴーは130年以上も前に見抜いていたのかもしれません。
おわりに
この本を読み終えて、なぜ自分が今こういう考えをしているのか、その根っこを示唆されたように思います。
ビゴーの絵に描かれた明治の人々――笑い、働き、迷い、そして懸命に生きる姿。それは現代の私たちにとっても変わらない「日本人の原点」なのかもしれません。
備忘します。
>
明治15年1月、日本の美術館に興味を持った1人の若いフランス人が日本にやってきた。ページ11
ジョルジュ・ェルナンフェルディナン・ビゴーは、1860年4月7日、パリの官吏の子として生まれた。画家である母の影響で小さい頃から興味を持ち、5歳にして周囲のものを驚かすほどの絵を描いた。ページ13
ビゴーは、明治14年12月11日にマルセイユからフランスの舟に乗り込み、香港で同じくフランス優先の船に乗り換えて明治15年1月26日に横浜に着いたのである。47日間の旅であった。ページ15
何人もの日本女性を愛し、そして別れた。明治32年6月に帰国する時、日本女性佐野まさとの間にもうけたフランス国籍の息子ガストンモリスを連れて行った。ページ19
ビゴーは1927年昭和2年、パリ郊外で去った。明治中期の歴史的事件にことごとく顔出す歴史証言者としての面、ワーグマンとともに日本の近代化がに与えた影響面、陸軍士官学校での画家教師、様々な画集の刊行。黒田清輝との交渉等の近代美術の中での行動面から彼の業績をもう一度見直す必要がある。ページ20
条約改正は居留地の廃止を意味した。居留地での自由な出版活動が生活の基礎だったビゴーにとって、新条約の実施はこの絵のように妻子と路頭に迷うことを意味していた。思い悩んだ末、彼は妻と別れ、フランス国籍の子供を連れて帰国する決意をした。ページ40
ビゴーの家には、日本の未開振り、非近代的側面を諸外国にPRしようとする意図が含まれている。ページ46
出っ歯の男を描いているが、その口の形が魚によく似ていて、しかも自身が魚屋であることがおかしかったのである。このような作品にも、日本人に出っ歯が多いという観念を植え付けるのに寄与しているのであろう。ページ53
近代化は日本の社会の支柱を精神主義から物質主義へと駆り立てていた。人口の増大、欲望の増大などによって、すべて金を中心に考える世の中へと変身しつつあった。そこがビゴーにとってたまらなく寂しかった。ページ55
昭和初期にはソフトが大流行し、男性の外出時の冠帽率95%ということであった。帽子をかぶらない方が肩身が狭い時代だったのである。ページ66
江戸時代の川柳、「役人の骨っぽいのは猪牙(チョキ)に乗せ」を思い出す。収賄しない役人は、猪牙舟に乗せて吉原へ連れて行き、「飲ませる、抱かせる、握らせる」の策略をめぐらすのである。汚職は明治になっても相変わらず行われていたし、現代では猪牙舟よりももっと巧妙な手段によって同じようなことが行われている。ページ70
江戸時代になって銭湯が普及しですと風呂場で脱いだ着物を包み、浴後にこれを敷いて着衣したところから風呂敷と呼ばれるようになったと言う。その便利さにはビゴーも驚かされた。ページ81
女性がこんなにあけすけだったのは、男もかなり解放的だったからであろう。このそのようにふんどし1本で町中を歩く男もそう珍しくはなかった。ベージ96
明治時代、遊郭として認められていたのは吉原、品川、新宿、板橋、千住の五箇所で、明治9年に根津が加わり、明治21年まではこの六箇所であった。ページ98
江戸時代の銭湯は混浴が多く、風紀の取り締まりが度々出されていたものの、ほとんど効果はなかった。明治5年4月、東京は混浴禁止の通達を出したが、浴槽に仕切り板1枚を貼り渡す処置を取る程度で、そんな板もすぐに外されたりした。混浴風呂が都市から消えるのは明治10年代である。しかし地方の温泉へ行けば、まだまだ家族風呂や夫婦風呂といわれる混浴や大根浴場があった。ページ106
外国人にとって浴場は最も衝撃的な風俗だった。ビゴーも例外ではなかったが、彼はその衝撃が感動に転じて銭湯ファンになってしまった。温泉の混浴風呂には何度も出かけたらしく、そのスケッチは多い。ページ108
最近は下水道設備も普及し、肥たご車もバキュームカーも目しなくなったが、40年前の日本は、まだこの世と同じ状態だった。日本人の悪臭への無感覚さにパリ育ちの画家は閉口してる。ページ129
明治31年2月に刊行された画集の中にあるこの絵は、日本に自動車がいつ入ってきたかを証言する貴重な資料だと私は思っている。ページ200
この漫画は、日清戦争後の極東の劣等感の思惑を非常にうまく描いている。左端のイギリスが日本をけしかけてロシアに対抗させようとしている。友人とタバコをくゆらしておる不気味なロシアに、日本はどんぐりまなこで恐る恐る近づこうとしている。ページ214
新条約実施後極めて悲観的に見ていたビゴーは、同朋に今の日本からの引き上げの時であることを告げようとしたのかもしれない。自身も、心の中で帰国の準備をしていたのである。ページ226
近代化は日本人の欲望を刺激しながらどんどん進んでいった。すなわち、洋服、帽子、靴が欲しい、洋食を食べたい、電気を使い、ガラス戸のある家に住みたい、写真館へ写真を撮りに行きたい…と洋風生活への憧れが金の執着心を強くした。ページ138
<<