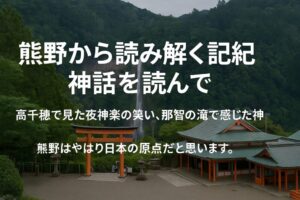人生100年時代と呼ばれるいま、その意味を改めて考えさせられる一冊がありました。
📖 書名:『100年の旅人 ネバーエンディングジャーニー』
この本に書かれていることは、正直なところ、私にとっては驚くような内容ではありませんでした。
むしろ、今の自分の考えと重なる部分が多く、
「やはりそうだよな」と確認できた感覚です。
上手く言葉にできなかった部分が、この本によって言語化され、思考の整理ができたのが最大の収穫でした。
心に残ったフレーズ
🔸「高齢社会に必要なのは、“高齢者が増える社会”に新しい視点を持つこと」
👉 若者中心の社会像から離れ、“生涯現役”**という価値観に目を向ける必要がある。
🔸「思い立った時が、いつでも出発点」
👉 年齢に関係なく、自分が“やってみたい”と思った時がスタート。
人生において、もう遅いということはない。
🔸「時間こそが、人生最大の財」
👉 お金や地位よりも、自分の時間をどう使うか。
その使い方こそが、“ミッション”の本質である。
🔸「好きだからやっている」
👉 何よりもシンプルで、でも一番強い理由。
今、自宅が「基地」になる時代へ…けれど
この本では、自宅を“ホーム=拠点”として、
そこから創造や挑戦を広げるライフスタイルが提案されています。
たしかに、在宅ワークやDIY、家庭菜園など、
自宅でできることは増え、「暮らしの中で完結する」機能も高まりました。
しかし一方で、自宅を“基地”にしすぎることで、
引きこもりがちになる
気分転換が難しい
孤立しやすくなる
といったリスクも無視できません。
私自身、この点には賛同しきれない部分があります。
やはり、人との接触や環境の変化こそが、創造や気づきの起点になることも多いからです。
「自宅を起点としつつも、社会とつながり続けること」——
そのバランス感覚が、100年人生を生きるうえで大切なのではないかと感じました。
最後に:夢が現実を変えるということ
Dreams make real. Real makes dreams.
ここでいう「夢が現実を変える」は、
よく聞く “Dreams come true(夢は叶う)” とは少し違います。
これは、ただ願っていれば夢が自然に実現するという受動的な意味ではなく、
「夢」が行動を生み、「現実」を動かし変えていく原動力になるという意味です。
そしてまた、変化した現実が、次の夢を育てていく。
そのダイナミズムの中にこそ、私たち一人ひとりの「旅」があるのだと思います。
備忘として、ここに記しておきます。
>
高齢社会を研究すれば明確にわかることが1つそれは何か。高齢社会に必要なのは若い社会を中軸にしたまま高齢者が多くなる、と言う視点ではなく、高齢者が多くなって若い人が減るという社会に対して、新しい視点を持つことである。言い換えれば、誰もがみんな生涯現役であるということだ。ページ27
個人が強く興味を刺激され、関心を持ったテーマを生涯かけて学習し、探求し続けることができる社会。しかも人生の時間はたっぷりあるから、それが何歳であっても構わない。よしやろうと思い立てば、それは常に出発点である。それが長く現役で生きる、100年人生の叶えてくれるダイナミズムであるはずだ。ページ28
所有については、腹八分。可能な限り分かち合いの中でシェアするのは当然であり、個人が独占を主張するものに対しては厳しくのも突きつける。これを論理ではなくむしろ直感する感性としてぶつけてきている。ページ35
…従来に固執する人は覚悟を問われ、そうでない人は、楽しく気軽に、面白く参加し、人生の旅へと入っていくことができるだろう。我々が一人ひとり、個人に戻るのは、そうした変化に向けて、より素直に足元を見直し、何を継続すべきかを確認するためである。ページ55
時間こそが人生最大の財である。我々は日常の中でミッション使命という言葉を使う。それは命や時間の使い方のことなのだ。健康と言うのも寿命のこと、実は時間だ。こうして考えると、時間をただ時を刻むと言う意味合いを超えて、実にがたい時間財なのである。ページ64自宅を拠点としてのホーム単位での自己解決、自己創造は生涯を舞台に、大きく広がっていく。家の中で自ら問題を解決する。家の中で欲しいものを作り、必要なことを片付ける。ページ86
日々、小さくてもいいからトライアルをするということを紛れ込ませ今日の手ごたえを掴み、違いを大切にしながら積み上がっていく。これが100年人生のライフデザインだ。ページ129
新しい時代に重要な事は、好きだからやっているである。ページ158
夢を持たなければ現実を変えることはできない。夢が現実を変え、その現実が夢を作るのだ。DreamsメイクリアルリアルメイクDreamsということである。ページ166
ポイントは継続と変化。成し遂げ、楽しみ、生涯の時間をかけて納得のいくまで、追いかけ続ける。そのために必要な情報の理解と共有についても、いくつかの視点から思いを巡らせてみた。ページ178
<<