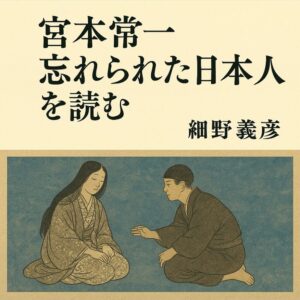オウンドメディアを「従たる考え」から「主たる考え」へ
Webマーケティングは難しい、と常々感じていました。本書を読み、オウンドメディアの重要性を改めて再確認しました。これまで「補助的な手段」として捉えていたものを、経営の中心に据えるべきだと痛感しました。
著者はベンチャー企業「フリーセル」の木村裕紀社長。中小ベンチャー向けに書かれていますが、零細企業にとってはさらに特異な戦略が必要だとも感じました。資金も人材も乏しい中でのマーケティングは、まさに生き残りをかけた「ゲリラ戦」。ヒット・アンド・アウェーを繰り返しながら、成果を積み重ねていくしかないと考えます。
ブランドとは「らしさ」
ブランドとは何か。本書では強引に一言で言えば「らしさ」だと定義しています(p.8)。この「らしさ」を表現するのが広告やロゴ、コピーなどであり、顧客だけでなく社員、株主、社会全体に伝わっていきます(p.10)。
特に心に残ったのは、ブランドを構成する要素として挙げられた5つのポイントです(p.11)。
・理念としての存在意義
・ビジョンという未来像
・コーポレートストーリー
・行動指針や価値観
・競合優位性(USP)の明確化
これらを磨き上げ、一貫性を持たせることこそがブランディングだと説かれています。
一貫性こそブランドの砦
自らを振り返ると、ホームページ、LP、チラシ、会社案内、Facebook投稿、メルマガ…すべてが統一されていなければブランド構築はできないことに気づかされました。インターネットの登場により、零細企業でもニッチ市場でブランド戦略を試行できるのは大きな幸運です。
「社会性・独自性・経済性の順番で考えよ」という言葉(p.40)も印象的でした。右肩上がりの時代は経済性を優先しても通用しましたが、今は違います。まず社会や顧客に対してどのような価値を提供するかを考え、次に差別化を図り、結果として利益がついてくる。これは小さな企業ほど肝に銘じるべきだと思います。
オウンドメディアの力
ブランドが確立すれば顧客は「これこそ自分が求めていたものだ」と共感し、リピーターやファンへと育っていきます(p.53)。そのためには、オウンドメディアの立ち上げと一貫性ある運営が欠かせません。
特に中小企業にとっては、インターネット広告がニッチ戦略と相性が良く(p.75)、経営者のパーソナルブランドと企業ブランドが一致しやすい点が強みとなります(p.79)。
オウンドメディアは採用・集客・取引先開拓という3つの場面で大きな効果を発揮し、将来の「無形資産」を育てる取り組みとも言えるでしょう(p.134)。
零細企業のブランド戦略に向けて
結局のところ、零細企業の生き残り戦略は「自社のらしさ」をいかに発見し、表現し、一貫して伝え続けられるかに尽きるのだと思います。すぐに大きな成果は望めませんが、積み重ねが未来をつくります。
そして最後に印象に残った一文――「成功している人に共通しているのは、明るく、元気で、素直であること」(p.176)。小さな会社だからこそ、まずはこの姿勢を忘れずに歩み続けたいと思います。
備忘します。
>
ブランドとは何か? 話を進めるために、やや強引に一言で言ってしまうと、それは「らしさ」ということに突き詰められるのではないかと思います。ページ8
例えば広告等は、こうした「らしさ」の表現ということができるのでしょう。企業の表明を感じているのは、顧客だけでに限りません。社会、株主、そして社員なども含むすべてのステークホルダーです。ページ10
…ブランドはいくつかの要素から構成されていますが、重要なのは次の5つに要約することができると私は考えています。
・理念としての存在意義
・ビジョンという目指す未来
・創業から今日までのコーポレートストーリー
・大切にしている行動指針や社是、社風、価値
・USB (競合優位性)の明確化
ブランディングはこれらの各要素を磨きつつ、そこに一貫性を持たせる取り組みということができます。ページ11
情報流通量と情報消費量のギャップが拡大する中で、多くの企業は顧客や取引先、人材マーケットなどに対して、特徴的なフレーズやイメージを届けようと苦労しています。そこで鍵を握るのがブランドです。自社の「らしさ」を的確に表現するブランドメッセージやロゴ、コピーなどを通じて相手に強い印象を残すことができれば、そのメッセージはコップ(相手の脳)の中に位置を占めることができるでしょう。ページ26
では土台とは何か? それは自社の存在意義としての理念であり、社是や行動指針、それを体現する経営者や幹部、社員たちです。また自社の「らしさ」に共感して応援してくれる顧客、ファンと呼べるような人たちも土台を構成する要素に加えることができるでしょう。ページ27
土台要素としての理念は、存在意義と言い換えることができます。何のためにそのビジネスを行っているのか、社会に対してどのようなインパクトを与えたいと考えているのか、そこには創業の志が反映されているはずです。ページ32
次にビジョンです。ビジョンとはこうなりたいという将来像だといえます。ビジョンが曖昧だと、幹部や社員の方向感が定まりません。バラバラな方向に向かって各自が頑張っても大きなパワーが生まれませんから、企業には明確なビジョンが必要になるわけです。ページ33
企業にとってもぶれないこと、一貫性を持つ事は極めて重要なのはいうまでもありません。それはブランディングに取り組む際の、最も注意すべきポイントと言えるでしょう。逆に見れば、ブランディングを見直し整理していく事は、企業の一貫性を維持することにも効果があるはずです。先にブランディングが企業の砦となると書いた意味もここにあるのです。ページ35
…講義の中で特に印象的だったのは、「社会性、独自性、経済性」の順番で物事を考えなさいという大久保氏の言葉です。かつては、もっぱら経済性と独自性を追求し、申し訳程度に社会性を考えるという企業も多かったように思います。右肩上がりの時代はそれでも一定の成長を遂げることができます。しかし今は違います。最初に考えるべきは、社会や顧客に対してどんな価値を提供する会社なのか、どうやって世の中を良くしたいのかということです。次に差別化を図り、他社にないものを提供するための方法を工夫します。これらを適切に実行できれば結果として利益が上がり、企業は成長続けることができる。ページ40
次にブランディングの効果として見ていくのは、顧客取引先の創造です。企業の目的は、顧客の創造であるとは、経営学の創始者といわれるピータートラッカーの有名な言葉です。ページ52
ブランドが確立していれば、自社の強みや特徴がわかりやすくなります。顧客や市場は共感ポイントを看取しやすくなります。端的に言えば、これが求めたいものだと感じる人が増えるのです。自社の商品やサービスに接して貢献した人たちの中には、リピーターやファンになってくれる顧客も現れるでしょう。ページ53
ここでのポイントは、まず自社のブランドイメージを固め、特徴的なオウンドメディアを立ち上げてプロモーションを実行すること。このアプローチにより、大きな成果を生み出すことができました。オウンドメディアを作る際には、ブランディング、ユニーク・セリング・プロポジション(USB)の明確なことも大切です。USBとは自社が持つ独自の強みのこと。顧客や市場に対する、差別化されたメッセージということができるでしょう。CIとUSBが一致すると、力強いコミニケーションデザインを生み出すことができるのです。ページ55
中小ベンチャー企業にとって重要な点は、インターネット広告がニッチに適していることです。ページ75
企業規模が小さいほど、パーソナルブランドと企業ブランドを一致させやすい。これを強みとして、中小ベンチャー企業の経営者が活用しない手はありません。ページ79
媒体とは距離を置く中小ベンチャー企業にとって、アウターブランディングの主役を担うのはオウンドメディアです。…繰り返しになりますが、オウンドメディアを構築する上で注意すべきは一貫性です。ページ114
ブランドロゴは、基本的にすべてのオウンドメディアに形成される重要なものです。あらゆるタッチポイントで反復されることに大きな意味があります。ページ119
採用、集客。取引先という3つの観点で、オウンドメディアは重要な役割を担っています。そして、自社のコンテンツを拡充しながらオウンドメディアを育てていく事は、将来の無形簿外資産を作り出す喜びの大きな仕事です。ページ134
成功している人に共通している要素は、「明るく、元気で、素直だ」ということです。明るい人には将来を見る力が備わっていて、すべてをチャンスに変えることができます。ページ176
<<