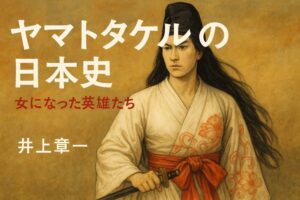「松本清張で読む昭和史」を読みました。
本書では「点と線」「砂の器」「日本の黒い霧」「昭和史発掘」「神々の乱心」といった松本清張の代表作を通じて、昭和という激動の時代を読み解いていきます。
清張は小説でありながら、その中にノンフィクションに匹敵する鋭い取材や史実を盛り込み、圧倒的なリアリティを感じさせます。現実と小説の境界を超える作風は、読者に深い印象を与えます。
清張という作家
松本清張は41歳という遅いデビューで学歴もなく、九州の田舎から才能だけを武器に上京して大作家になったという非常に稀有な存在です。
だからこそ、社会の底辺で暮らす庶民や虐げられた人々の視点で物語を描き、圧倒的にリアルな人間描写ができたのだと思います。
「点と線」
「点と線」は、以前に読んだような記憶はあるものの詳しくは思い出せません。むしろテレビドラマや映画で楽しんだ印象が残っています。
小説の最大のトリックに使われた東京駅のホームの配置などはすべて事実に基づいており、物語の土台をリアルにすることで強い説得力がありました。
だからこそこの小説は古びることなく、人間の心理や欲望の普遍性を描き続けているのだと思います。
「砂の器」
「砂の器」は映画で見ました。美しい映像と、あの名曲「宿命」に胸を打たれた記憶があります。
物語の背景には、かつてのらい病患者に対する理不尽な隔離政策・差別が描かれています。
高度成長期の中で、日本がどんどん新しく生まれ変わる一方で切り捨てられていく人々の存在に、清張は鋭く目を向けました。
「日本の黒い霧」
「日本の黒い霧」は単なる陰謀論ではなく、戦後の日本の裏側に潜む黒幕の存在に迫るものです。
特にGHQの影がどこまで関与していたのかという視点は興味深く、占領期という特殊な時代に鋭い問いを投げかけています。
ただし要約だけでは伝わりきらず、原著を読んでこそ理解できる重厚なテーマだと感じました。
「昭和史発掘」
226事件を深く掘り下げた「昭和史発掘」は、非常に重要な問題提起をしています。
わずか数日で18人に死刑判決が下された理由、昭和天皇と母・貞明皇太后の確執、秩父宮の存在など、これまで見えなかった構造に切り込んでいます。
反乱軍である中橋や磯部らが宮城を占拠し、天皇と重臣の連携を断って天皇を自分たちの手中に収める計画があったという清張の指摘は衝撃的でした。
さらに貞明皇太后が弟の秩父宮を天皇にしたかったのではないかという疑惑も提示し、兄弟間の対立や宮中の政治闘争が古代さながらにあったことを示唆しています。
「神々の乱心」
「神々の乱心」では、貞明皇太后が大正天皇の死後も皇太后として強い影響力を保ち続けたことが描かれています。
女性が持つ権力の性質や、昭和期の宮中での人間関係の複雑さを清張らしいリアリズムで活写しており、まさに清張作品の集大成のように感じました。
この作品を通して、戦地から帰還した将軍たちが天皇と貞明皇太后の両方に報告に訪れていたという事実も紹介され、宮中の実態に迫る筆致には驚かされます。
天皇の「祈り」とその継承
そして現代において、2011年の東日本大震災での天皇陛下のテレビメッセージは強く記憶に残っています。
あの放送で国民を直接励ましたことは、災害に見舞われた人々に大きな安心感を与えました。
また天皇が「象徴天皇」としての務めに国民の安寧と幸せを祈ることを位置づけ、皇居の宮中三殿で神々に向かって祈るという祭祀を続けている姿に、古代からの連続性を感じました。
現代の天皇もまた「神に仕える存在」であるという本質を再確認させられた思いです。
おわりに
松本清張はフィクションの中に緻密な取材を織り込み、リアルな歴史像を提示する稀代の作家です。
人間の欲望や弱さ、悲しみを描く筆致は今なお古びることなく、昭和を知る貴重な手がかりになります。
備忘します。
>
「点と線」はもちろんフィクションですが、東京駅のホームの位置関係などは全て事実に基づいています。…つまり、1番重要なトリックの部分が事実に基づいているわけです。ページ33
にもかかわらず関わらにもかかわらずこの小説はなぜ古びないのか、それはやはり先程述べたように人間が抱えている心理や欲望というものは根本的に変わっておらず、男女の性別を超えて読者が登場人物に感情移入できる余地が残っているからだと思います。ページ46
「砂の器」が描くのは、高度成長期の日本です。戦前の日本がどんどん刷新され、古いものが捨てられ、ものすごい勢いで新しいものに変わっていく時代です。その過程において、いわば振り落とされて忘却されていくものがあったわけですが、清張はそこから目を離しませんでした。ページ70
…米軍基地の存在というものはある種のブラックボックスです。治外法権になっていて、日本がにありながら簡単には中に入れない。また特に占領期についていえば、当時駐留していたGQの人たちは、清張が日本の「黒い霧」を書き始めた頃には既に日本からいなくなっていましたから、直接会うことはできません。…つまり清張にとっては残された資料を手がかりにするしかないという根本的な壁が存在したわけです。ページ100
「昭和史発掘」は膨大な資料と綿密な取材に基づいて清張が書き上げた、普及のノンフィクションの作品です。「日本の黒い霧」が連載された当時よりも10年ほど前の過去を対象したのに対してこの作品はさらに遡り、連載された当時よりも30年から40年前の加工対象したことになっています。ページ112
当時公表された獄中手記で、磯部は昭和天皇に対する激しい怒りを綴っていました。自分たちは「国体」を曇らしている「君主の奸」を排除した。この行いを必ずや天皇は理解してくれる、自分たちを褒めてくれる違いない。そう信じて待っていたのですが、結果は全く逆で天皇は彼らの行動に激怒しました。そのことに対し、磯部が憤怒をあらわにしたわけです。ページ126
つまり中橋や磯部らには、宮城を占拠し天皇と重心の連携を遮断して昭和天皇を自分たちの手中に収める計画があったというのが、清張が昭和市発掘で明らかにしたことでした。ページ130
とは言え貞明皇后と昭和天皇の確執、あるいは秩父宮と昭和天皇ないし貞明皇后の関係、ここに早々と目をつけた清張は鋭いと思います。清張だからこそなしえた大きな発掘。これらを20年以上の時を経てつなげてみせたのが、清張最後の小説「神々の乱心」なのです。ページ158
日中戦争及び太平洋戦争の時期、戦地から帰ってきた軍人の多くが、昭和天皇とその母である貞明皇后の両方に報告に訪れているということです。ページ180
もう一つは先ほどから触れている、女性が持っている権力性を書くということです。「神々の乱心」を読むと、大正天皇が亡くなった後に残った皇后が、皇太后としてその後も君臨しているという昭和初期の宮中の実態と言うものが見えてきます。ページ192
2011年3月11日に起こった東日本大震災では、5日後の3月16日天皇自身がテレビに出演し国民を直接励ましました。天皇がテレビに出演し、用意してきたお言葉を読み上げたのは、これが初めてでした。政府や議会を飛び越え、天皇が国民と一体となったのです。この放送は、地震や津波、原発事故により、かつてないほど大きな不安が広がっていた人を落ち着かせて、天皇に対する崇敬を呼び起こす上で圧倒的な影響力をもたらしました。ページ209
天皇自身が象徴とは何かを定義したお言葉にも注目しておく必要があります。ここで天皇は、象徴天皇の務めとしての1つとして、国民の安寧と幸せを祈ることを挙げています。これは祭祀祭祀、すなわち皇居の宮中三殿でアマテラスなどの神々に向かって祈るという行為を意味します。ページ211