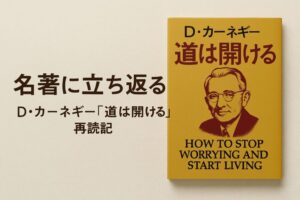先日、「noteの書き方収益化攻略ガイド完全版」をKindleで読みました。タイトル通り、noteで収益化を目指すための実践的なノウハウが詰まった一冊でしたが、それ以上に、「書くとは何か?」をあらためて問い直すきっかけにもなりました。
空白と改行は“リズム”を作る
まず、目からウロコだったのが「空白と改行の使い方」。文章を読みやすく、心地よく届けるには、内容だけでなく“見た目のリズム”が大事。改行ひとつで読み手の負荷が下がり、自然と文章に引き込まれていく感覚が生まれます。
タイトルは最後に決める
タイトルは「記事の顔」。私は今まで書きながらタイトルを何度も迷っていたのですが、著者は“本文を書き終えた後”に、もっとも印象的なキーワードを拾い、心に刺さるタイトルを練り上げていました。納得です。
キャプション画像や目次、そしてSEOの基本
画像の使い方も「読者の視線を止める工夫」としてとても参考になりました。目次を入れるだけで離脱率が下がるというのも納得ですし、SEO対策として「本文とタイトルに読者ニーズのあるキーワードを自然に盛り込む」点もシンプルかつ本質的でした。
他SNSとの連携:note × X × Instagram × Threads
驚いたのはSNS連携の細やかさ。X(旧Twitter)での要点投稿、Instagramストーリーズでのリンク共有、Threadsでの共鳴…など、note単体で完結せず、各SNSの特性を活かして記事を届けていく戦略は非常に実践的でした。
「フォロー戦略」とは
フォロワーの増やし方についても、闇雲にではなく、自分の興味と関心軸で“読んでくれそうな人”にアプローチする。共感と関心の共鳴を意識した、正攻法の積み重ねが書かれており、勉強になりました。
ライティングは“サービス”である
一番心に残ったのは、「ギブアンドギブアンドギブ」。書くことを“自己表現”ではなく、“誰かのためのサービス”と捉え、見返りを求めず、ただひたすら与え続ける。読んでもらう前提で、徹底的に読みやすく、気持ちを込めて届ける姿勢。まさに、サービスの神様。
実体験こそ最強のストーリーテリング
体験談、特に失敗談は強い武器になる。読み手の共感を呼び、物語性を持った文章は記憶に残る。これはすぐにでも取り入れたいテクニックです。
【これからの自分へ】
この本を通じて、noteを「ただ書く場」ではなく、「読んでくれる人の人生の一瞬に寄り添う場」として捉える視点が生まれました。
そして何より、「最後まで読んでくれた方に御礼を言う」こと。これは今まで意識していませんでしたが、これからは必ず、言葉にして届けたいと思います。
🌱最後まで読んでくださって、ありがとうございます。
この記事が、あなたのライティングや発信活動のヒントになれば嬉しいです。
備忘します。
「文章を書く」と考えると固くなりがちですが、 要は、自分の心の中から湧き出たものを、 どんな表現であれ、自由に形にしていくことが大切なんです。読んでもらいたいな、と思う「読者像」を思い浮かべながら書く。 それだけで、不思議と、書きたいことが自然に湧き上がってくることがあるんです。だいたい2,000文字以上になることが多いですが、 テーマによっては6,000文字に達することもありますし、 写真メインの記事では1,000字に満たないこともあります。
最近は「文字数カウントメモ」(無料アプリ)も愛用中。
大切なのは、 「閃きを逃さないこと」 「思いついた瞬間に、回収すること」。
感情は、記憶と共に、時間が経つと薄れてしまうからこそ。 「速く書く」ことで、記憶と感情の鮮度を保てるのです。
「いつでもどこでもライティング脳の作り方」は 閃いたらすぐ書く
メモの習慣をつける スマホでもパソコンでも気軽に書く 速く書いて勢いを育てる ご褒美を用意して楽しむ 自分のリズムを信じる こんな、小さな習慣の積み重ねです。
【タイトルは文章を書き終えて決定する】
タイトルは、記事の顔。読者が最初に出会う「入口」です。 私はまず、仮タイトルをつけて文章を書き始め、すべて書き終えたあとに文章全体を見渡して、もっとも心に刺さるキーワードや印象的な言葉を拾い直して、タイトルを最終決定しています。
「タイトルで惹きつける力」は、noteに限らず発信全般においてとても重要です。
ここでは、私が実際の記事を作るときに意識している、タイトル設計の8つのポイントをご紹介します。①意外性のあるタイトルを意識する
突然、妻が映画「アイアンマン」を見始めたあの日、在宅勤務が崩壊したことは誰も知らない。年収2000万円の内定先から逃げ出したあの夏の日が人生最良の選択 驚きやユーモアがあると、読みたくなる。
②読者に問いを投げかける
なぜnoteを書き続ける人に共感するのか。同志感を覚えてしまうのか。 読者の「自分ごと」に引き込む力がある。
③気持ちがほっこりする温かい感じのタイトル
午前5時のファミマにサービスの神様がいる幸せ 感情に寄り添い、癒しや優しさを感じてもらう。
④数字を入れる
「書かずにはいられない衝動」を引き出す5つの名言
⑤感情表現をストレートに出す
「極悪女王」は極上の胸熱青春ドラマだ!一気に観て、興奮して、最後に泣いた全5話鑑賞レビュー! 「愛の不時着」に今更ハマって泣いて笑ってトキめいた15の理由
⑥短くスパッと断言する 答えは自分で出すしかない。シンプルな力強さが印象を残す。
⑦流行したフレーズをアレンジする
共通テストで漏らすは恥だが役に立つ。 noteで夢を語ることの大切さと温かさと心強さと 親しみや面白さ、共感が生まれる。
⑧Google検索のキーワードも意識する「書き出しは“つかみ”が命」とよく言われますが、私はそれよりも、 書き手の人柄がにじみ出るような“感情の流れ”を大切にしています。
加えて、記事内で使う太字も、いきなり結論を強調するためではなく、ポイントをひとつずつ丁寧に提示するために使うことで、読み手が自然と文章に引き込まれていきます。
一方で、私が映画レビューやK-POPのライブレポを書くときは、最初の一文で「最高だった!」「心震えた!」と感情の沸点を一気に放つように書きます。…こうした「沸点から始まる文章」は、読者にとっても「お、この人めちゃくちゃ熱いな!」と引き込まれる要素になります。
写真を早い段階で入れるのもおすすめです。【締めの言葉には想いや熱量を込める】
文章に“熱”は宿るか?私は、はっきりと「ある」と信じています。 人が心から発した想いには、目に見えないけれど、確かに“熱”があります。その熱は、文章を通して読む人の心に伝わり、共鳴し、震えさせ、動かす力を持っています。締めの言葉には、ぜひあなたの“熱”を込めてください。【最後まで読んでくれた方に御礼を書く】
noteの記事を最後まで読んでもらえるということは、読者の方が、あなたの言葉と“共に旅をしてくれた”ということです。 だからこそ、「読んでくださってありがとうございます」の一言を、記事の最後にそっと添えてみてください。【ストーリーテリングを豊かに──実体験を書こう】
ストーリーテリングとは、体験談やエピソードなどの「物語」を通じて、伝えたい思いやコンセプトを読み手に印象づける印象づける表現手法です。…特に効果的なのが、実体験をベースにしたストーリー。 そして中でも──失敗談は、最高のストーリーテリングの材料になります。
ヒーローズ・ジャーニーの3つのステージ 1.Separation「別れ・旅立ち」「Calling 呼びかけ」 2.Initiation「通過儀礼」 慣 3.Return「帰還」
試練に立ち向かい──そしてついに、勝利を掴み、もとの場所に帰還する。
【冒頭を会話からスタートする】
ストーリーテリングのテクニックとして、もうひとつお薦めしたいのが「冒頭を会話から始めること」です。
【実体験を小説風に書く】
あの時、私は――ぎりぎりの判断を迫られていた。でも、あの時の判断があったから、今の自分がいる。…「臨場感」や「物語性」を持たせて描くと、読者をグッと惹き込む力が強まります。
【結論をあえて最初に言わず、サスペンスを創る】
…結論を最初に言わない方が効果的な場面もあります。 それは、ミステリーやサスペンスのように、読み手の興味を引きつけたいとき。【あえて改行を多めにする】
一文一文が、美しく際立ち、 リズム良く流れていく── そんな文章の連なりが好きだからです。そのために大切なのが、「余白」です。そして、余白を生み出すのが「改行」です。
【見出し画像を楽しんで工夫する】
記事の第一印象を決める大きな要素── それが「見出し画像」です。
noteでは、自分の好きな画像を自由に設定することができます。【文頭に目次を入れる】
明らかに「目次を入れた方が、最後まで読まれる率が高まる」のも事実です。【目次の設定方法】
noteで目次を設定する方法は、とても簡単です。文章を書く列の左側にある「+」ボタンをクリックすると、目次を挿入できる選択肢が表示されます。また、「記事全体の構成を事前に確認したいな」と思ったら、画面左上の三本線(≡)をクリックすると、見出しごとの目次が表示されます。【写真/音声/動画の活用】
写真・音声・動画の活用についてお話したいと思います。リンクを貼っておくことで、文章と音楽を一緒に楽しめる空間を届けています。自分の心に問いかけてほしいのは 「それが読者の役に立つ情報なのか?」 「その情報は、誰かにとって“今、必要なこと”なのか?」 という視点です。 そして、この視点をふまえて、有料記事を書く際に 一番意識してほしいのが、「読者の悩みを解決すること」です。
SNSでシェアする
【X(旧Twitter)でシェア】
私は、記事を書いたら必ずX(旧Twitter)でシェアしています。 また、Instagramのストーリーズにリンクを貼り、ジャンルごとにハイライトに保存するようにもしています。noteとXは連携できます。
①記事の要点をツイートにまとめる▶ 詳しくはこちら!(note記事リンク)#
②リツイートされやすい投稿を意識する
③記事紹介の切り口を変えて複数回投稿する
【Instagramのストーリーズ・通常投稿で拡散する】
①ストーリーズでnote記事リンクを貼り、投稿するnoteのアプリにはInstagramのストーリーズに投稿するというシェア機能もあります。
②ハイライトを活用する ストーリーズのリンク付き投稿をハイライトにカテゴリ別に保存する。
③ 「通常投稿」で記事リンクに誘導する 見出し画像と記事の前半を投稿。記事の要点やはChatGPTで要約、関連ハッシュタグをつけて、1記事ごとに時間帯を分けて複数回投稿する。【Threadsの特徴と、noteとの相性】
①趣味や思想、感性でつながる“クローズド共鳴”が強い
→ noteに興味がある人と、自然につながりやすい空気感があります。
②最大500文字まで投稿可能
→ note関連の発信をしている方をフォローし、同時にThreadsのプロフィール欄にnoteのリンクがあれば、noteもフォローしていくと、noteへの関心がが深い層と繋がれます。【フォロワーを正攻法で増やしていく】
フォロワー数の増加=リーチできる読者の数を増やすことが不可欠です。中でも最も効果が高かったのはフォローです。フォローには制限がありますが、1回で最大15人、1日では最大100人までのフォローが可能です。
どんな人をフォローすると効果的か?私は以下の3タイプにアプローチしていました。
①自分が興味のあるノートクリエイターをフォローしている人
②自分が関心のある#で記事を書いている人
③ノートを始めたばかりで、投稿内容が自分の興味と一致する人
フォロワー数が1000人を超えたあたりから、興味ある方に絞って返すようなスタイルに変えていきました。
【マガジン機能】
記事をまとめることができるマガジン機能がありますこのマガジン機能を上手に活用することで単発読書を継続して読んでくれるファンへと育てる仕組みを作ることができます。
①読者として使うお気に入り記事ストック紹介する
②書き手として使う自分の作品をまとめて世界観を伝える
【SEO対策の根本を知る】
私はシンプルに本文に記事の内容のキーワードを複数入れるということを意識して多くの記事がGoogle検索上位を獲得しています。私はタイトルと本文に検索ニーズに合ったキーワードを盛り込みながら、読み手の感情を揺さぶり、共感を呼ぶことを大切にして記事を仕上げてきました。
実はSOの革新ってすごくシンプルなんです。それは検索エンジンに好かれる記事を書くこと=読書に喜ばれる記事を書くことです。
Googleが掲げる銃の真実ユーザを第一に考えれば全てが後からついてくる。
【お勧めのSEO対策サイト】
①ラッコキーワード ワーラッコキーワード例えばノート有料ノートなど気になるキーワードを入力するとその周辺で検索されている関連ワードが一覧で表示されます。
②アラマキジャケット こちらは入力したキーワードがYahoo!やGoogleで月にどれくらい検索されているか調べることができます。そして最後に私がもう一つ実践していることがありますそれは、記事の末尾に関連記事のリンクを貼ること。
最終章
【サービスの神様になりきろう】
読む方へのサービス精神を忘れないこと…誰かの心に届く文章を書きたいのならば、自己表現欲求を100に対してサービス精神は120でいきましょう。…読んでくれる人のために書くと言う姿勢を貫いてみてください。
サービス精神旺盛な文章とは?
①読みやすくわかりやすい文章
②読み手が楽しめる文章にする
③役立つ情報が含まれている文章
④シンプルで平明な文章
⑤太字や絵文字でリズムをつける
⑥トレンドや話題性のあるテーマを扱う
一番番読んで欲しい人を想定して書く。これはターゲットを明確にして想像して書くということです。
起承転結にこだわらず、結論から書く。つまり、結論→詳細(理由)→結論の流れですねこの構成に。具体例を加えるとよく知られているPR EP法になります。
①ポイント(結論)
②Reason (理由)
③エグザンプル(具体例)
④ポイント(結論)
これはウェブライティングの基本形です。
読み手の目線に合わせてコミュニケーションを取る。不満、批判などネガティブな事は書かない。ポジティブな感情を起こさせる記事を書く。例え話でイメージしやすくする【ギブアンドギブアンドギブ】
徹底したサービスの神様になろうというテーマです。見返りを求めない精神で一つ一つの記事を誰かのために気持ちを込めて書くことが何より大切です。
人生は短い。だからこそワクワクすることをしよう。私は、ただそのワクワク感に導かれるままに、ノートと出会いそしてはまった。