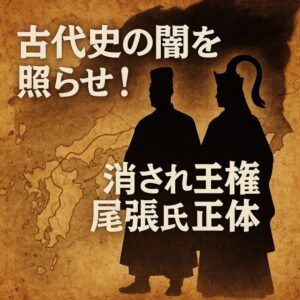先日、『日本史の新常識』という最近の研究成果をアンソロジー形式でまとめた本を読みました。多彩な分野の研究者による知見が集約され、まさに“歴史の新地平”を体感できる一冊でした。私が漠然と“常識”だと思い込んでいた歴史観が覆されるような内容が多く、改めて「日本史は奥が深い」と痛感させられました。以下、心に残ったポイントをまとめます。
大友皇子があっけなく敗れた理由
「壬申の乱」では、大友皇子が短期決戦で敗北したことが有名ですが、その背景として『日本史の新常識』では、「新羅への支援に多くの物資・兵力を割いてしまった」ことが指摘されています。大友側は白村江(663年)の敗北後、新羅への対応に忙殺され、兵士・物資の補給にも追われてしまった。一方、吉野にいた大海人(後の天武天皇)は、兵の補充や軍事物資を着実に確保したため、勝利を収められたといいます。結果として、大友皇子は自らの外交的選択が仇となり、滅びに至ったわけです。
“銅銭導入”と世界商品としての硫黄・銀
日本に大量の銅銭がもたらされた理由としては、宋で紙幣が流通するようになり、余った銅銭を周辺国が引き取ったという視点が新鮮でした。中国中心の交易や経済情勢が、日本の貨幣事情を大きく左右していたのです。
また、日本が世界経済の中で重要な役割を果たした例として、10世紀頃に硫黄が突然“世界商品”となったことや、16世紀には銀が世界を席巻したことが挙げられます。硫黄は宋で火薬が実用化されたことによって需要が爆発し、銀は石見銀山の精錬技術革新によって大量生産が可能になった。いずれも「中国の需要×日本の資源」という構図が見事に噛み合った事例で、当時の国際情勢における日本の存在感を改めて認識させられました。
豊臣政権滅亡の真相と“血統”の問題
豊臣政権の終焉について、秀頼が秀吉の実子であることを周囲が信じ切れなかったという記述は衝撃的でした。血筋の正統性に疑いがある状態での後継者では、武功派大名の支持を得ることが難しかったのでしょう。こうした“後継者問題”が政権の土台を揺るがし、最終的には豊臣家の滅亡を導いたという解釈は、従来の「家康の策略」だけでは語れない複雑な背景を感じさせます。
江戸時代から始まっていた近代化
徳川幕府の社会システムは近代化の礎であった――この主張はこれまでも言及されてきましたが、本書では改めて「江戸時代における産児制限」など、社会制度が近代化をスムーズに進める素地になっていたと紹介されていました。都市部の識字率の高さや商業・流通網の発展はもちろんのこと、人口動態も近代化に影響していたことを再確認させられます。
留守政府による改革の推進力
「米欧回覧実記」に登場する岩倉使節団の留守政府が、思いのほか近代化を進める原動力になったという視点も新鮮でした。要職の政治家が海外に行っている間、それぞれの省が独創的に改革を進めた結果、行政面での進歩が促進されたというのです。中央のトップダウン型だけでなく、ボトムアップの改革が合わさることで国家の近代化が進んだという構図は興味深く、まさに歴史のダイナミズムを感じました。
昭和の戦争指導者たちの“西郷幻想”
また、西南戦争を振り返ることで、大東亜戦争(太平洋戦争)へ突入していった昭和の指導者たちの精神構造が読み解ける、という主張も印象的でした。西郷隆盛が起こした内戦の記憶が、革命的な行動や精神論を過度に美化し、戦争と革命の論理を混同してしまった――。こうした分析は、昭和史を語るうえでの新たな視点を与えてくれます。
読了しての感想
本書では、日本史の各時代における新研究の成果が散りばめられており、読者の“常識”や“イメージ”をことごとく覆す内容が満載でした。
どれもただ単に「出来事」を追うのではなく、当時の国際情勢や人々の心理、外交や資源など、多角的な分析に基づいて歴史が解き明かされていく点が非常に興味深かったです。
特に「私たちが当たり前のように持っている歴史観を、最新の研究によってアップデートしていく」ことの大切さを痛感しました。自分の知識や見方が誤っていたと気づかされるのは一瞬ショックですが、それを乗り越えて新しい知見を得られるのは、とても刺激的で楽しい体験です。
おわりに
『日本史の新常識』は、日本史好きの方はもちろん、これから勉強しようという方にもおすすめできる一冊でした。多くの専門家の研究成果をざっくりと把握できるので、興味を持ったトピックがあれば、さらに深掘りするきっかけにもなります。
今回取り上げた内容はほんの一部。まだまだ未知の論点や新説が盛りだくさんなので、引き続き他の章も読み進めながら、私自身の“日本史像”をアップデートしていきたいと思います。歴史は時代ごとに研究が進むからこそ、常に新しい“常識”を学び直す余地がある――この本を通して、そんな当たり前でいて新鮮な事実を、改めて再認識しました。