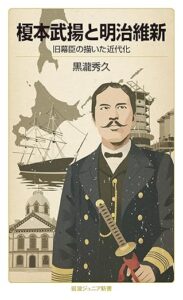date: 2025-04-01
30年経っても色褪せないテーマ
約30年前に出版された『天皇の起源』。読み始める前はさすがに古い内容かもしれないと思っていましたが、驚くほど今の自分にも響いてきました。もちろん、考古学やDNA解析などの最新知見を踏まえると補足が必要な点もあるかもしれませんが、核心となるテーマには今も変わらぬ普遍性があります。
天皇は神か、人か?
懐かしい三島由紀夫の「天皇は神である」という立場が言及されていましたが、本書はむしろその逆を行きます。天皇を「即神」とはせず、神と人との間にある存在として描いています。
特に心に残ったのは、大嘗祭の描写です。
大嘗祭は天皇が神を食べ、自ら神になる密儀である。(p.215)
即位の儀式というより、神秘的な転換の儀式。単なる統治者ではなく、神に最も近い「媒介者」としての姿が印象的でした。
「上記」と「富士古文書」?偽書かもしれないが…
本書では、『古事記』『日本書紀』以外にも「上記(じょうき)」や「富士古文書」といった古史資料があることが紹介されています。いずれも偽書の疑いが濃いとされつつも、それでも「語り継がれていること」の意味を考えさせられます。
また、徐福伝説と天皇のつながりについても触れられており、日本列島の中で交わった様々な文化の痕跡を感じました。
昭和天皇の「人間宣言」を改めて知る
マッカーサーとの面談エピソードはよく知られているものの、昭和天皇が「持っていないものを捨てろと言われても困る」と述べたという記録(p.94)は初めて知りました。この言葉には、日本人の精神文化と「象徴としての天皇」の在り方がにじみ出ていると感じました。
天皇は「神に仕える人間」だった
天皇はこの世の外にある不可視の神々に対しては人間であり、人間に対しては現人神であった。(p.452)
この一節には深くうなずかされました。天皇が「神」ではなく、「神を祀り、神と向き合い、神の声を伝える存在」であったからこそ、歴史の荒波を乗り越えて存続してきたのだと思います。
神道は日本列島で生まれた
神道はどこまでも日本の宗教である。(p.251)
この言葉も忘れがたいものです。外来宗教のように布教しない、日本列島の中で独自に生まれた信仰。だからこそ、神道と天皇は切り離せない存在として今に至るのだと納得しました。
自分はどこから来たのか——神社巡りの原点
私は普段から神社を訪れるのが好きで、無意識のうちに「自分はどこから来たのか」を探していたのだと思います。本書はその問いに対して、歴史・思想・宗教の側面からヒントを与えてくれました。
現代は「神のラッシュアワー」
現代はむしろ多すぎる神々の時代、宗教のラッシュアワーである。(p.202)
科学や合理主義が進んだ現代でも、信仰は消えるどころか、むしろ多様化している――この指摘には、どこかほっとするものがありました。
読むきっかけは「保守とは…」の言説
SNSで「保守とは、家族を大事にし、地域を大事にし、天皇陛下を尊敬することだ」という言葉を目にしたのが、本書を手に取ったきっかけです。あまりに単純化された定義かもしれませんが、それが気になったからこそ、「天皇とは何か」をもっと知りたくなりました。
おわりに
『天皇の起源』は、単なる歴史書ではありません。
私たち日本人のアイデンティティを静かに、しかし深く揺さぶる書物です。
「天皇は神か?それとも人か?」という問いに対し、本書はそのどちらでもなく、「祈る人」であり続けた存在としての天皇像を提示しているように感じました。
自分のルーツに興味がある方、日本の宗教文化や思想に関心がある方には、ぜひ一度読んでみてほしい一冊です。
markdown終わり
必要であれば、アイキャッチ画像や引用のレイアウト(ブロッククオートなど)もWordPressに合わせて整えますので、お申し付けください。また、SNS用に短縮バージョンも作成可能です。