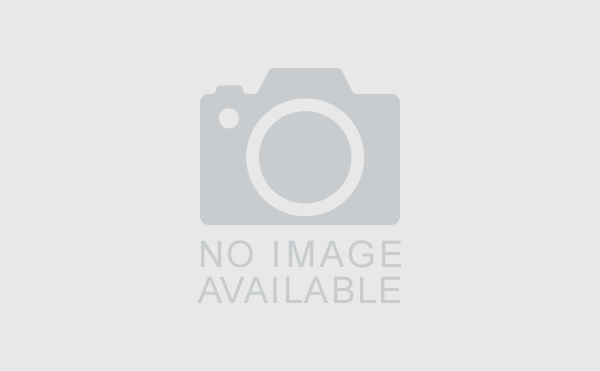ユヴァル・ノア・ハラル氏の「緊急提言 パンデミック」を読みました。「サピエンス全史」「ホモデウス」の著者が人類の歴史を俯瞰して、今回のコロナ禍を語っています。歴史的なパンデミックの様相と決着、克服のための基本的態度について語っています。中国が悪いとか、グローバリズムが原因だとかの言説を誤ったものと断じています。「ウィルスが歴史の行方を決める事はない」「この危機がどのような結末を迎えるかは、私たちが選ぶ」テクノロジーには頼るべきだが、結局は人類そのものの対応が試されているとの意見です。備忘します。

- 作者:ユヴァル・ノア・ハラリ
- 発売日: 2020/10/07
- メディア: Kindle版
…私たちが直面している最大の危機はウィルスではなく、人類が内に抱えた魔物たち、すなわち憎悪と強欲と無知だ。私たちは今回の危機に臨んで、憎しみを燃え上がらせることもできる。…だが、憎悪や強欲は無知を生み出すような反応を見せる必要はない。思いやりや気前の良さや英知を生み出すような叡智を生み出すような対応もとりうる。ページ10
…壁を築き、移動を制限し、貿易を減らせと。だが、感染症を封じ込めるのに短期の隔離は不可欠だとはいえ、長期の孤立主義政策は、経済の崩壊につながるだけで、真の感染症対策にはならない。むしろ、その正反対だ。感染症の大流行への本当の対抗手段は、分離ではなく協力なのだ。ページ15
今回の危機の現段階では、決定的な闘いは人類そのものの中でこる。もしこの感染症の大流行が人間の間の不安と不信を募らせるなら、それはこのウィルスにとって最大の勝利となるだろう。人間同士が争えば、ウィルスは倍増する。対照的に、もしこの大流行からより緊密な国際協力が生じれば、それは新型コロナウィルスに対する勝利だけではなく、将来現れるあらゆる病原体に対しての勝利ともなることだろう。ページ30
この危機に臨んで、私たちは2つの取り分け重要な選択を迫られている。第一の選択は、全体主義的監視下か、それとも国民の権利拡大というものだ。第二の選択は、ナショナリズムに基づく孤立か、それともグローバルな団結か、と言うものだ。ページ35
…だが、プライバシーと健康のどちらを選ぶかと言うことが、実は問題の根源になっている。なぜなら選択の設定を誤っているからだ。私たちは、プライバシーと健康の両方を享受できるし、また、享受できてしかるべきなのだ。ページ43
ウィルスを打ちまかすために、私たちは何をおいても、グローバルな形で情報を共有する必要がある。情報の共有こそ、ウィルスに対する人間の大きな強みだからだ。ページ48
私たちは、感染症に対処するにあたっては科学を信頼するべきだが、自分は一時的な存在であり、必ず死ぬという事実に取り組む責務も、依然として担わなくてはならない。ページ71
第二の大きな危険は、新型コロナウィルスの変異です。これは決して忘れてはなりません。ウィルスが広まり、長い時期、人間の間に止まれば、その分だけウィルスが変異する可能性が増えます。その結果、ウィルスは感染症が強まったり、致死性が高まったりするでしょう。ページ76
1918年から翌19年にかけて、世界中でインフルエンザスペイン風が流行しました。実際には、このパンデミックには第一波に加えて、第二波と第三波がありました。第一波は1918年の春に起こり、全世界で何百万人もの人が感染しましたが、致死性はあまり高くなく、亡くなる人もそれほど多くなく、流行は下火になりました。ところがその後、ウィルスが変異し、強力で事情に感染性が強く、致死性もはるかに高いものに変わり、秋に第二波が起こりました。このウィルスが大勢の命を奪ったのです。ページ77
独裁者は迅速に動けます。誰とも相談する必要がないからです。ところが彼らは間違いを犯すと、それを認める事はまずありません。隠します。メディアを支配下に置いていますから、隠蔽するのは簡単です。ページ83
歴史的視点から広く見渡してみると、新型コロナウィルス感染症の流行は、監視の歴史における重大な転換点、大きな変化の時になる可能性があります。ページ85
私たちは、緊急事態の時に何かをして、これはこの危機の間だけの措置だ、危機が過ぎれば、前と同じ普通の状態に戻れるというものですが、それは幻想に過ぎません。緊急事態や緊急措置は一人歩きを始めがちで、当初の状況が変化してから長い時間がたっても、継続する傾向にあります。ページ96
要するに、パンデミックに対する現実的な対策は、遮断ではなく、協力と情報共有です。新型コロナウィルスに対する私たちの最大の強みは、ウィルスにはできない形で協力できることです。ページ102
…まずはその入り口にたどり着かなくてはならない。それは容易ではないが、「ウィルスが歴史の行方を決める事はない」「この危機がどのような結末を迎えるかは、私たちが選ぶ」
、テクノロジー、特に強力な監視テクノロジー自体も、決して悪いわけではなく、私たちがどう活用するか次第であると言うハラリ氏の言葉を肝に銘じながら進んでいくべきなのだろう。ページ125